パソコンの心臓部!「ブート」ってなに?

ITの初心者
先生、「boot」ってどういう意味ですか? コンピューターを起動するって意味らしいんですけど、どうして「boot」って言うんですか?

ITアドバイザー
良い質問だね! 実は「boot」は「靴」と同じ単語なんだ。コンピューターを起動することを「boot」って言うのは、ちょっと面白いでしょ?

ITの初心者
えー! 靴と関係あるんですか? どうしてですか?

ITアドバイザー
昔はね、コンピューターを動かすには、最初に小さなプログラムを読み込む必要があったんだ。そのプログラムを「ブートストラップローダー」って言って、これがコンピューター自身を起動させるために必要な、もっと大きなプログラムを読み込む役割をしていました。 つまり、小さなプログラムが、大きなプログラムを引っ張り上げる、まるで「靴紐を引っ張って長い靴を履く」ようなイメージだったことから、「boot」が使われるようになったんだよ。
bootとは。
「コンピューターに関係する言葉、『boot』(コンピューターを動かすこと。電源を入れてから、コンピューターを動かすためのソフトウェアが動き出すまでの一連の作業を指す。『ブートストラップ』とも言う。⇒起動)について」
パソコンを動かすための魔法
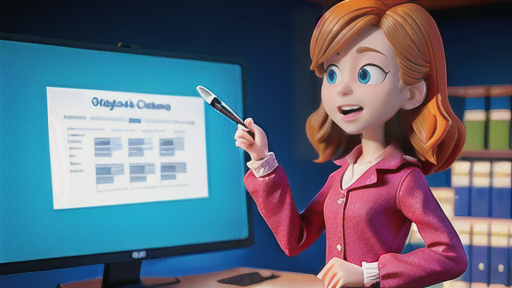
皆さんは、パソコンの電源ボタンを押すと、どのようにして画面に文字や絵が表示されるのか、不思議に思ったことはありませんか?まるで魔法のように、一瞬でパソコンが目覚めるその裏側には、「ブート」と呼ばれる重要なプロセスが隠されています。
ブートとは、電源投入からOS(オペレーティングシステム)が起動するまでの、いわばパソコンを目覚めさせるための準備運動のようなものです。電源ボタンを押すと、まずパソコンに内蔵されている小さなプログラムが動き出し、ハードウェアの動作確認を行います。これは人間で例えるなら、寝起きに体の一部がちゃんと動くか確認するようなものでしょうか。
その後、この小さなプログラムは、パソコンの脳みそに当たるCPUや記憶装置であるメモリなどを起動し、OSが起動するための準備を整えます。そして、いよいよOSが起動し、普段私たちが目にするパソコンの画面が表示されるのです。
このように、パソコンを動かすためには、目には見えない多くのプログラムが連携して、複雑な作業を行っています。まるで魔法のように感じるのも無理はありませんね!
| プロセス | 内容 | 人間に例えると |
|---|---|---|
| 電源ボタンを押す | パソコンに電源が入る | 目を覚ます |
| 小さなプログラムが起動 | ハードウェアの動作確認を行う | 寝起きに体の一部がちゃんと動くか確認する |
| CPUやメモリなどを起動 | OSが起動するための準備を整える | 脳や体が完全に目覚める |
| OSが起動 | 普段私たちが目にするパソコンの画面が表示される | 活動開始! |
ブートの舞台裏をのぞいてみよう

パソコンの電源を入れると、画面に様々な表示がされて、やがて見慣れたデスクトップ画面が現れます。この起動するまでの過程を「ブート」と呼びますが、一体どのような仕組みで動いているのでしょうか?
ブートは、いくつかの段階を経て行われます。まず、電源ボタンを押すと、パソコンに内蔵された小さなプログラムが動き出します。このプログラムはBIOSやUEFIと呼ばれ、パソコンの心臓部であるCPUやメモリ、ハードディスクなどのハードウェアの動作確認を行います。この段階で、パソコンが正常に動作するかどうかをチェックしているのです。
次に、BIOSやUEFIは、OSが格納されているハードディスクやSSDといった記憶装置を探し出し、そこから必要なデータを読み込みます。ハードディスクやSSDは、膨大な量のデータを保存できる装置ですが、OSを起動するために必要なデータはほんの一部です。BIOSやUEFIは、この必要なデータだけを的確に見つけ出し、メモリに読み込む役割を担います。
そして、OSがメモリに読み込まれると、いよいよOSが起動します。OSは、パソコン全体を制御する役割を担っており、アプリケーションソフトを実行したり、ファイルを管理したりするために欠かせないものです。OSが起動すると、デバイスドライバと呼ばれるプログラムが読み込まれ、キーボードやマウス、ディスプレイなどの周辺機器が使えるようになります。こうして、私たちが普段見ているデスクトップ画面が表示され、パソコンが使える状態になるのです。
ブートにかかる時間は?

パソコンを立ち上げてから操作ができるようになるまでにかかる時間、いわゆる起動時間のことですが、これはパソコンによってまちまちです。一体なにが起動時間の長さに関係しているのでしょうか?
パソコンの性能は、起動時間に大きく影響します。最新のCPUやメモリを搭載した高性能なパソコンは、処理速度が速いため、起動も速やかに行われます。反対に、古いパソコンでは処理能力が低いため、起動に時間がかかってしまうのです。
記憶装置の種類も、起動時間に関係します。ハードディスクドライブ(HDD)よりもSSDを搭載したパソコンの方が、データの読み書き速度が圧倒的に速いため、起動時間が大幅に短縮されます。
また、パソコンにインストールされているソフトウェアの数も、起動時間に影響を与えます。起動時に自動で立ち上がる設定になっているソフトウェアが多いほど、その分起動時間が長くなってしまいます。
最近の技術の進歩により、高性能なパソコンやSSDが普及してきたことで、起動時間が数秒から数十秒と、以前に比べて格段に短くなっています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| パソコンの性能 | CPUやメモリが高性能なパソコンほど、起動時間が短い |
| 記憶装置の種類 | SSDを搭載したパソコンは、HDD搭載のパソコンよりも起動時間が短い |
| インストールされているソフトウェアの数 | 起動時に自動で立ち上がるソフトウェアが多いほど、起動時間が長くなる |
「ブートストラップ」って?

「ブートストラップ」とは、コンピュータ用語で、パソコンの電源を入れてからOSが立ち上がり、操作できる状態になるまでの一連の起動過程を指す言葉です。
「ブート」という言葉を聞いたことはありませんか?実は、「ブート」は「ブートストラップ」を省略した言葉なのです。「ブートストラップ」は、靴のかかとについている、紐を通すための輪っかのことを指します。そして、「ブートストラップ」には「自分の力で引っ張り上げる」という意味があります。
では、なぜコンピュータ用語に「ブートストラップ」が使われているのでしょうか?それは、パソコン自身が自らを起動させる様子が、まるで「自分の力で引っ張り上げている」ように見えたからです。
つまり、パソコンの電源投入時に、OSを起動するために必要なプログラムを読み込み、実行するという、一見複雑に見える過程も、「ブートストラップ」という言葉で表現できるのです。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ブートストラップ | パソコンの電源を入れてからOSが立ち上がり、操作できる状態になるまでの一連の起動過程 |
| ブート | ブートストラップの省略形 |
| 由来 | 靴のかかとについている、紐を通すための輪っか。「自分の力で引っ張り上げる」という意味がある。 |
| コンピュータ用語での意味 | パソコン自身が自らを起動させる様子が、まるで「自分の力で引っ張り上げている」ように見えることから。 |
ブートはパソコンの健康状態のバロメーター

パソコンを起動する際にかかる時間は、パソコンの健康状態を測る一つの目安になります。いつもより起動に時間がかかると感じたら、それはパソコンのどこかに不調が起きているサインかもしれません。
起動時間の長さの原因は様々です。例えば、パソコンの主要記憶装置であるハードディスクが故障すると、データの読み書きに時間がかかり、起動が遅くなることがあります。また、パソコンの作業領域であるメモリが不足している場合も、起動が遅くなる原因の一つです。
さらに、パソコン起動時に自動で立ち上がるソフトが多い場合も、起動時間の長さに影響します。必要のないソフトが起動時に読み込まれていると、その分起動に時間がかかってしまうのです。
日頃からパソコンの起動時間や動作に気を配り、いつもと違うと感じたら注意深く観察することが大切です。少しでも異変を感じたら、専門家に相談するなど、早めに対策を講じましょう。
| パソコン起動時間 | 状態 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 長い | 不調 |
|
専門家への相談など、早めの対策 |
