実行時エラー:原因と対策

ITの初心者
先生、『実行時エラー』ってどういう意味ですか?

ITアドバイザー
そうですね。プログラムを作ったとき、実際に動かしてみるまで気づかないエラーのことです。例えば、計算しようとしたときに、ゼロで割ってしまうような場合が考えられます。

ITの初心者
作ったときは問題なくても、動かすとエラーになるんですね。他にどんな例がありますか?

ITアドバイザー
例えば、無いはずのファイルを開こうとしたり、使えるはずのない部品を使おうとしたときなどですね。プログラムを作るときは、こういう実行時エラーが起きないように、きちんと確認する必要があるんですよ。
実行時エラーとは。
情報技術において、プログラムが実際に動いている最中に発生するエラー、いわゆる『実行時エラー』について説明します。
実行時エラーとは

実行時エラーとは、作った仕組みが実際に動いている時に起きる不具合のことです。不具合は、仕組みの組み立て方の間違いや、予想外の出来事が起こった時に発生します。
例を挙げると、数をゼロで割ろうとしたり、無い書類を開こうとしたり、記憶が足りないのに作業を続けようとすると、実行時エラーが発生します。仕組みが普通に動いている時は問題ありませんが、特定の状況になると実行時エラーが発生することもあります。そのため、実行時エラーは仕組みを作る段階だけでなく、実際に使う段階でも気を付けなければならない問題です。
実行時エラーが起こると、仕組みが急に止まったり、予想外の結果を出したりする可能性があります。場合によっては、仕組み全体に影響する大きな問題に発展することもあります。例えば、工場のベルトコンベアを制御する仕組みで実行時エラーが発生すると、ベルトコンベアが急に止まり、工場全体の生産に影響を与える可能性があります。また、銀行の口座管理システムで実行時エラーが発生すると、預金の引き出しができなくなったり、残高が正しく表示されなくなったりする可能性があります。
そのため、実行時エラーが発生した場合は、すぐに対応する必要があります。不具合の原因を探し出し、適切な対策を施すことで、仕組みの安定した動作を維持することができます。具体的には、エラーが発生した時の状況を記録したり、仕組みの動作を詳しく調べたりすることで、原因を特定します。そして、プログラムの修正や、記憶容量の追加など、適切な対策を行います。
このように、実行時エラーは様々な場面で発生する可能性があり、システムに深刻な影響を与える可能性もあるため、注意が必要です。日頃から実行時エラーへの対策を意識することで、より安定したシステムを構築することができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 作った仕組みが実際に動いている時に起きる不具合 |
| 原因 | 仕組みの組み立て方の間違いや、予想外の出来事 |
| 例 | ゼロ割、存在しないファイルのオープン、メモリ不足 |
| 発生時期 | 仕組み作成段階、および、使用段階 |
| 影響 | 仕組みの停止、予想外の結果、システム全体への影響 |
| 具体例 | 工場のベルトコンベア停止、銀行システムの障害 |
| 対応 | 原因究明、プログラム修正、記憶容量追加など |
| 対策の重要性 | システムの安定稼働に必要 |
主な種類
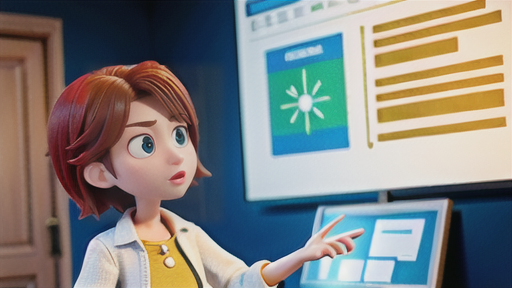
プログラムを動かしている時に発生する、実行時エラーには様々な種類があります。実行時エラーは、プログラムの書き間違いや、プログラムが想定していない状況になった時に起こります。主な種類を説明します。まず、ゼロで割るエラーは、計算で数値をゼロで割ろうとした時に発生します。例えば、ある数を計算結果で割る場合、その計算結果がゼロになってしまうと、このエラーが発生します。次に、ファイルがないエラーは、存在しないファイルを扱おうとした時に発生します。例えば、読み込もうとするファイル名が間違っていたり、ファイルが削除されていると、このエラーでプログラムが止まります。それから、記憶容量不足エラーは、プログラムを動かすのに必要な記憶領域が足りない時に発生します。大きなデータを取り扱うプログラムや、長時間動作するプログラムで起こりやすいエラーです。また、型変換エラーは、異なる種類のデータを互換性のないように変換しようとした時に発生します。例えば、文字列を数値に変換しようとした際に、文字列が数字ではない場合にこのエラーが発生します。さらに、配列の範囲外アクセスエラーは、配列と呼ばれるデータの集まりで、存在しない場所にアクセスしようとした時に発生します。配列には番号が振られており、その番号の範囲を超えてアクセスするとエラーになります。これらのエラーが発生した場合、エラーの種類に応じた対策が必要です。ゼロで割るエラーであれば、計算結果がゼロにならないように処理を追加したり、ファイルがないエラーであれば、ファイルの存在を確認する処理を追加する必要があります。記憶容量不足エラーであれば、使用するデータ量を減らしたり、処理方法を見直す必要があります。型変換エラーであれば、変換前にデータの種類を確認する処理を追加する必要があります。配列の範囲外アクセスエラーであれば、配列の範囲を確認する処理を追加する必要があります。これらのエラーへの対処を適切に行うことで、プログラムを安定して動作させることができます。
| エラーの種類 | 説明 | 例 | 対策 |
|---|---|---|---|
| ゼロで割るエラー | 計算で数値をゼロで割ろうとした時に発生する。 | 計算結果で割る際に、計算結果がゼロになる場合。 | 計算結果がゼロにならないように処理を追加する。 |
| ファイルがないエラー | 存在しないファイルを扱おうとした時に発生する。 | 読み込もうとするファイル名が間違っている、ファイルが削除されている。 | ファイルの存在を確認する処理を追加する。 |
| 記憶容量不足エラー | プログラムを動かすのに必要な記憶領域が足りない時に発生する。 | 大きなデータを取り扱う、長時間動作する。 | 使用するデータ量を減らす、処理方法を見直す。 |
| 型変換エラー | 異なる種類のデータを互換性のないように変換しようとした時に発生する。 | 文字列を数値に変換しようとした際に、文字列が数字ではない。 | 変換前にデータの種類を確認する処理を追加する。 |
| 配列の範囲外アクセス | 配列で存在しない場所にアクセスしようとした時に発生する。 | 配列の番号の範囲を超えてアクセスする。 | 配列の範囲を確認する処理を追加する。 |
発生原因の特定

プログラムがうまく動かない時、何が原因なのかを突き止める事はとても大切です。そのためには、いくつかの手がかりを集める必要があります。まず、エラーメッセージをよく見てみましょう。エラーメッセージには、どんな種類のエラーなのか、なぜ起こったのかといったヒントが隠されています。エラーの種類が分かれば、解決の糸口を見つけやすくなります。次に、エラーが起きた時間を確認します。いつエラーが起きたのかを知ることで、原因を特定しやすくなります。例えば、特定の時間にサーバーに負荷が集中していた、といった原因が見えてくるかもしれません。それから、プログラムのどこでエラーが起きたのかを特定します。プログラム全体を見直すのではなく、エラーが起きた部分に注目することで、効率的に原因を調べることができます。問題のある命令を特定できれば、修正も容易になります。さらに、プログラムが動いている環境も確認してみましょう。使っている機械の種類や設定、ネットワークの状態など、様々な要因がエラーに関係している可能性があります。例えば、必要な部品が足りていない、設定が間違っている、ネットワークが繋がらないといった状況が考えられます。これらの情報を一つ一つ確認することで、原因を特定しやすくなります。集めた手がかりを組み合わせ、全体像を把握することで、真の原因にたどり着くことができるでしょう。原因究明は地道な作業ですが、一つずつ丁寧に確認していくことが、問題解決への近道です。
| 手がかり | 詳細 | 利点 |
|---|---|---|
| エラーメッセージ | エラーの種類、発生理由のヒント | 解決の糸口発見 |
| エラー発生時間 | 発生時刻 | 時間帯特有の原因特定(例:サーバー負荷) |
| エラー発生場所 | プログラムの特定箇所 | 効率的な原因調査、修正容易化 |
| プログラム実行環境 | 機械の種類、設定、ネットワーク状態 | 環境要因特定(例:部品不足、設定ミス、ネットワーク接続不良) |
対処方法

プログラムが動作中に予期せぬエラーが発生した場合、その種類や原因に応じて様々な対応策があります。慌てずに状況を把握し、適切な処置を行うことが大切です。
まず、エラーメッセージをよく確認しましょう。メッセージにはエラーの種類や発生場所に関する情報が含まれており、迅速な解決の糸口となります。例えば、「数値を零で割ろうとしました」というメッセージであれば、計算式を見直す必要があることが分かります。
エラーの原因がプログラムの誤りである場合、該当箇所を修正する必要があります。変数の値が想定外の数値になっている、もしくは条件分岐の判定が誤っているといった単純なミスが原因であることも少なくありません。プログラム全体を丁寧に確認し、誤りがないかを確認しましょう。
プログラム自体に誤りがなくても、予期せぬ状況が発生した場合に備えて、あらかじめエラー処理を組み込んでおくことが重要です。例えば、ファイルを読み込む処理で、ファイルが存在しない場合に備えて、代替処理やエラーメッセージを表示するといった対応が考えられます。これにより、プログラムが途中で停止してしまうことを防ぎ、利用者に適切な情報を伝えることができます。
また、コンピュータの環境設定が原因でエラーが発生することもあります。必要な機能が有効になっていない、もしくは設定値が適切でないといった場合、プログラムが正常に動作しないことがあります。設定内容を見直し、適切な値に変更することで、エラーを解消できる可能性があります。
プログラムが大量の記憶領域や処理能力を必要とする場合、コンピュータの資源不足が原因でエラーが発生することがあります。このような場合は、記憶容量を増設する、処理速度の速いコンピュータに交換するといった対応が必要となる場合もあります。
上記のような対処方法を状況に応じて適切に組み合わせることで、プログラムの実行時エラーによる影響を最小限に抑え、安定した動作を実現することができます。
| エラーの種類 | 原因 | 対応策 |
|---|---|---|
| プログラムの誤り | 変数の値が想定外 条件分岐の判定ミス |
プログラムの修正 |
| 予期せぬ状況 | ファイルが存在しないなど | エラー処理を組み込む (代替処理、エラーメッセージ) |
| 環境設定の問題 | 必要な機能が無効 設定値が不適切 |
設定内容を見直し、適切な値に変更 |
| リソース不足 | 記憶領域不足 処理能力不足 |
記憶容量を増設 処理速度の速いコンピュータに交換 |
| その他 | エラーメッセージの内容 | メッセージから原因を特定し対応 |
予防策

プログラムが正しく動くためには、実行時の不具合をあらかじめ防ぐことが大切です。そのためには、プログラムを作る段階から、いくつかの点に気を配る必要があります。
まず、データの種類を正しく使うことが重要です。例えば、数字を入れる場所に文字を入れてしまうと、プログラムがうまく動かなくなることがあります。それぞれのデータに合った入れ物を用意するように、プログラムでもデータの種類を正しく指定することで、このような不具合を防ぐことができます。
次に、不具合が起きた時のための対処法をプログラムに組み込んでおくことも重要です。これは、例えば、停電が起きた時に非常灯がつくように、予期せぬ出来事が起きた時でもプログラムが完全に止まってしまわないようにするための工夫です。これにより、利用者に大きな影響を与えることなく、プログラムを安全に停止させたり、復旧させたりすることができます。
さらに、プログラムを何度もテストすることも欠かせません。テストを繰り返すことで、隠れた不具合を見つけ出し、修正することができます。これは、建物を建てる前に模型を作って強度を確かめるようなもので、実際に利用者にプログラムを使ってもらう前に、問題がないかを確認する重要な作業です。
これらの対策に加えて、システムを定期的に点検し、状態を監視することも大切です。これは、車の定期点検と同じように、システムに異常がないかを確認し、必要に応じて部品を交換したり、修理したりする作業です。これにより、大きな問題に発展する前に、小さな不具合を早期に発見し、対応することができます。
このように、様々な工夫を積み重ねることで、実行時の不具合発生を抑え、安定したシステム運用を実現することができます。
| 対策 | 説明 | 例え |
|---|---|---|
| データの種類を正しく使う | データに合った型を指定し、不具合を防ぐ | 入れ物に合った物を入れる |
| 不具合発生時の対処法を組み込む | 予期せぬ出来事への対応策を準備 | 停電時の非常灯 |
| プログラムを何度もテストする | 隠れた不具合の発見と修正 | 建物の模型による強度確認 |
| システムの定期点検と監視 | 異常の早期発見と対応 | 車の定期点検 |
まとめ

プログラムを実行した時に発生する誤り、いわゆる実行時誤りは、開発や運用においてどうしても避けられない問題です。実行時誤りは、プログラムが予期せぬ状況に陥った時に起こり、システムの停止やデータの損失といった重大な問題を引き起こす可能性があります。そのため、実行時誤りへの適切な対応は、システムの安定稼働に不可欠です。
実行時誤りが発生した場合、まず大切なのは慌てずに、落ち着いて原因を探ることです。誤りが発生した時の状況や、表示されるメッセージを注意深く確認することで、問題の原因を特定することができます。原因が特定できたら、適切な対応を行いましょう。例えば、誤りの内容によっては、プログラムの修正が必要な場合もありますし、システムの設定変更で対応できる場合もあります。どのような対応が必要かは、誤りの種類やシステムの構成によって異なります。
実行時誤りを防ぐためには、プログラムを作る段階から細心の注意を払うことが重要です。プログラムの設計を綿密に行い、想定される様々な状況を考慮することで、誤りの発生を未然に防ぐことができます。また、プログラムを作成したら、十分な試験を行い、誤りがないかを確認することも重要です。試験では、様々な状況を想定し、プログラムが正しく動作することを確認します。
システムを安定して稼働させるためには、実行時誤りへの理解を深め、適切な対策を準備しておくことが重要です。誤りが発生した場合の対応手順を事前に確認し、適切な対処方法を身につけておくことで、いざという時に迅速かつ的確に対応できます。また、開発チーム内で情報を共有し、過去の誤りの事例や対応方法を共有することも大切です。過去の事例から学ぶことで、同じ誤りの再発を防ぎ、システムの信頼性を高めることができます。日頃から準備を怠らず、チーム全体で協力して取り組むことで、実行時誤りの影響を最小限に抑え、安定したシステム運用を実現することができます。
| 実行時誤り | 内容 |
|---|---|
| 概要 | プログラム実行時に発生する避けられない誤り。システム停止やデータ損失等の重大な問題を引き起こす可能性がある。 |
| 発生時の対応 | 落ち着いて原因を探る。状況やメッセージを確認し、原因を特定。プログラム修正やシステム設定変更など、適切な対応を行う。 |
| 予防策 | 綿密なプログラム設計、想定される状況の考慮。十分な試験による動作確認。 |
| 安定稼働のための対策 | 実行時誤りへの理解を深め、適切な対策を準備。対応手順の確認、適切な対処方法の習得。開発チーム内での情報共有、過去の事例の共有。 |
