実装:思い描いたものを形にする

ITの初心者
『実装』って言葉、よく聞くんですけど、実際にどういう意味なのか、よく分かっていません。先生、教えてください。

ITアドバイザー
そうですね。『実装』は、簡単に言うと『使えるようにする』ということです。例えば、新しい部品を機械に取り付けて、実際に動かせるようにしたり、新しい機能をプログラムに追加して使えるようにする、といったことを指します。

ITの初心者
なるほど。部品を取り付けるだけじゃなくて、実際に使えるようにするまでが『実装』ってことですね。プログラムだと、コードを書くだけじゃなくて、実際に動くようにテストするまでってことですか?

ITアドバイザー
まさにそうです。プログラムで言えば、書いたコードをコンピューターで動かして、ちゃんと動くことを確認するまでが『実装』と言えます。目的の機能が正しく動くように、調整したり、不具合を直したりすることも含まれますね。
実装とは。
情報技術の用語で『実装』というものがあります。これは、コンピューターの機械やソフトウェアに、新しい部品や機能を組み込んで、実際に使えるようにすることを指します。『インプリメント』や『インプリメンテーション』とも呼ばれます。
実装とは何か

「実装」とは、設計図を基に実際に形あるものを作る作業のことです。家を作ることを例に挙げると、設計図は家の間取りや外観を決めた計画書で、それに基づいて大工さんが家を建てる作業が実装にあたります。
情報処理の世界では、「実装」は主にプログラムや処理系を作る際に、設計した機能を実際に使える状態にするまでの一連の作業を指します。例えば、新しい会計処理ソフトを作る場合、まずどのような機能が必要か、どのような画面にするかなどを設計します。そして、その設計に基づいて、実際にプログラムを書き、動作するソフトを作り上げます。これが実装にあたります。机上の空論ではなく、実際に動くものを作る、いわばものづくりの最終段階と言えるでしょう。
具体的な作業内容としては、まず設計書に基づいてプログラム言語を用いて命令文を書き連ねていきます。この作業を「プログラムを書く」または「符号化」と言います。必要な部品を組み合わせる作業も含まれます。会計ソフトの例で言えば、計算機能やデータベースとの連携機能など、様々な部品を組み合わせて一つのソフトを作り上げます。また、既に稼働している仕組みに新しい機能を追加する作業も実装に含まれます。例えば、既存の会計ソフトに新しい税制に対応するための機能を追加する場合も、実装作業の一つです。
実装が完了したら、設計通りに正しく動くかを確認する作業を行います。これは「試験」と呼ばれ、様々な条件でソフトを動かしてみて、不具合がないかを確認します。もし不具合が見つかった場合は、原因を調べ、プログラムを修正します。この修正作業も実装の一部です。こうした一連の作業を通して、初めて仕組が利用可能な状態になります。実装は仕組み開発における重要な工程であり、実装の質が仕組み全体の性能や信頼性を大きく左右します。 実装を適切に行うことで、使いやすく、安定した仕組を作ることができるのです。
| 用語 | 説明 | 情報処理の例 |
|---|---|---|
| 実装 | 設計図を基に実際に形あるものを作る作業。ものづくりの最終段階。 | 設計した機能を実際に使える状態にするまでの一連の作業。プログラムを書き、動作するソフトを作り上げる。 |
| 設計図 | 家の間取りや外観を決めた計画書。 | どのような機能が必要か、どのような画面にするかなどを決めた計画。 |
| 実装作業 | プログラムを書く(符号化)、部品の組み合わせ、既存システムへの機能追加、試験、修正作業など。 | 計算機能やデータベースとの連携機能など様々な部品を組み合わせて一つのソフトを作り上げる。既存の会計ソフトに新しい税制に対応するための機能を追加する。 |
| 試験 | 設計通りに正しく動くかを確認する作業。 | 様々な条件でソフトを動かしてみて、不具合がないかを確認する。 |
実装の重要性

仕組みを作ることは、絵に描いた餅を本物にする最後の大切な仕事です。どんなに素晴らしい計画でも、実際に作る作業がしっかりとしていなければ、思った通りの成果は得られません。例えば、家を建てることを考えてみましょう。どんなに立派な設計図があっても、実際に建てる大工さんの腕が悪ければ、家は崩れてしまうかもしれません。同じように、仕組みを作る上でも、作る作業の良し悪しが、その仕組みの安定性、信頼性、そして使いやすさを大きく左右します。
作る段階では、計画通りに仕組みが動くように、細心の注意を払って作業を進める必要があります。小さなミスも見逃さず、丁寧に作業を進めることが大切です。同時に、決められた期間や使えるお金の中で、無駄なく作業を進めることも重要になります。限られた資源を有効に活用し、最大限の効果を得られるように工夫する必要があります。
作る作業の質を高めることは、最終的に出来上がるものの価値を高め、使う人の満足度を上げることに繋がります。高品質な仕組みは、使う人が快適に利用できるだけでなく、長く使い続けることができます。また、不具合やトラブルが少ないため、維持管理にかかる手間や費用も抑えることができます。
作る作業は、単に計画通りに作業をするだけでなく、様々な要因を考慮しながら、柔軟に対応していく必要があります。作業中に予期せぬ問題が発生することもあります。そのような場合でも、冷静に状況を判断し、適切な対策を講じる必要があります。また、使う人の意見を聞きながら、より良い仕組みになるように改善していくことも大切です。
このように、作る作業は、仕組みの完成度を左右する重要な仕事です。計画から運用まで、全ての段階で質の高い作業を心掛けることで、本当に価値のある仕組みを作ることができます。
| 段階 | 内容 | 重要性 |
|---|---|---|
| 計画 | 素晴らしい計画を立てる | 計画の良し悪しが成果を左右する |
| 製作 | 計画通りに、細心の注意を払い、ミスなく丁寧に作業を進める。期間や費用を考慮し、資源を有効活用する。 | 安定性、信頼性、使いやすさを左右する。品質は最終的な価値、満足度に繋がる。 |
| 運用 | 問題発生時に冷静な対応、利用者の意見を聞き改善していく。 | 高品質な仕組みは、快適な利用、長期使用、維持管理の効率化に繋がる。 |
実装の種類
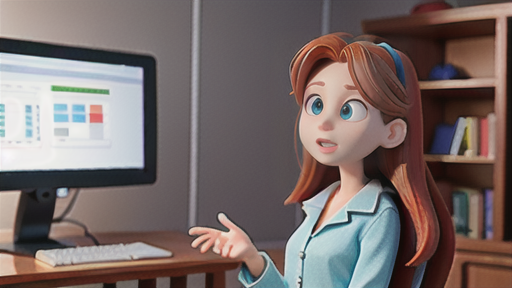
新しく仕組みを組み入れることを「実装」と言いますが、これは全く新しい仕組みを作るときだけでなく、今ある仕組みに新しい働きを付け加えたり、悪いところを直したりするときにも行います。
全く新しい仕組みを作るときは、何もないところから作り始めるので、大掛かりな作業になります。設計図通りに、一つずつ部品を組み上げていくようなイメージです。たくさんの部品を組み合わせて、大きな仕組みを完成させるには、多くの時間と労力が必要です。
一方、今ある仕組みに働きを付け加えたり、悪いところを直したりする場合は、既に動いている仕組みに影響を与えないように、細心の注意を払う必要があります。例えるなら、動いている時計の部品を交換するようなものです。時計を止めずに、部品を一つずつ丁寧に交換していくことで、時計を壊さずに修理することができます。
また、仕組みを組み入れるやり方には、少しずつ働きを公開していくやり方と、全ての働きを一度に公開するやり方があります。
少しずつ公開していくやり方は、利用者から早く意見を聞けるという利点があります。しかし、開発に時間がかかってしまうこともあります。
一度に全てを公開するやり方は、開発にかかる時間を短くできます。しかし、もし大きな問題が起きた場合は、影響が大きくなってしまうこともあります。
仕組みの大きさや種類、そして利用者の要望に合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。それぞれの方法には利点と欠点があるので、状況に応じて適切な判断をしなければなりません。
| 実装の種類 | 説明 | 例え | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 新規実装 | 全く新しい仕組みを作る | 何もないところから部品を組み上げていく | – | 大掛かりな作業で時間と労力が必要 |
| 機能追加/改修 | 今ある仕組みに働きを付け加えたり、悪いところを直したりする | 動いている時計の部品を交換する | – | 既に動いている仕組みに影響を与えないように注意が必要 |
| 公開方法 | 説明 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 段階的公開 | 少しずつ働きを公開していく | 利用者から早く意見を聞ける | 開発に時間がかかる |
| 一斉公開 | 全ての働きを一度に公開する | 開発時間を短縮できる | 大きな問題が起きた場合の影響が大きい |
実装の手順

物を実際に作り上げていく手順は、大きく分けて六つの段階に分けられます。まず初めに、計画を立てる段階です。この段階では、何をどこまで作るのか、どのくらいの期間で作るのか、どれくらいの人や費用が必要なのかといった、作る上での土台をしっかりと固める必要があります。次に、設計の段階です。ここでは、システム全体の構造や、一つ一つの機能について、細かい部分まで具体的に決めていきます。設計図を作るようなものです。三番目は、実際にプログラムを作る段階です。設計図に基づいて、部品を組み立てるようにプログラムを書き上げていきます。四番目は、テストを行う段階です。組み立てたものがきちんと動くか、不具合がないかを入念に確認します。五番目は、完成したものを実際に使えるようにする段階です。システムを動かせる状態にし、利用開始の準備を整えます。最後に、作ったものを維持していく段階です。システムが安定して動き続けるように、定期的に点検や修理、改良を行います。これらの手順は、システムの大きさや複雑さによって変わることもありますが、基本的な流れは変わりません。それぞれの段階で、適切な作業を丁寧に行うことで、質の高いシステムを作り上げることができるのです。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. 計画 | 何をどこまで作るのか、期間、人、費用など、土台を固める。 |
| 2. 設計 | システム全体の構造や機能を詳細に決定。設計図作成。 |
| 3. プログラム作成 | 設計図に基づき、プログラムを書き上げる。 |
| 4. テスト | 動作確認、不具合チェック。 |
| 5. 運用開始 | システムを稼働状態にし、利用開始準備。 |
| 6. 維持 | 定期点検、修理、改良。 |
実装と関連用語

新しく作った仕組みや道具を実際に使えるようにすることを、よく「実装」と言います。この「実装」と似た言葉に「導入」と「展開」があり、これらは混同しやすい言葉です。
まず「導入」とは、新しい仕組みや道具を組織の中に取り入れることです。たとえば、新しい会計処理の仕組みを会社に取り入れる、新しい道具を工場で使い始める、といった場合です。導入は、実装と重なる部分もありますが、導入の方がより広い意味を持っています。新しい仕組みを導入するには、仕組みを実際に使えるようにするだけでなく、使う人への教え方や、その仕組みを動かすための役割分担などを決める必要もあります。つまり、実装は導入の一部と言えるでしょう。
次に「展開」とは、完成した仕組みや道具を実際に使える状態にすることです。たとえば、新しい販売管理の仕組みを全国の支店すべてで使えるようにする、といった場合です。多くの場合、展開は実装の一部として行われます。新しい仕組みを実際に使えるようにするには、その仕組みを必要な場所に設置し、調整する必要があります。これはまさに展開という言葉が表す意味です。
まとめると、実装とは仕組みを「使えるようにする」ことで、導入とは仕組みを「使い始める」こと、そして展開とは仕組みを「利用可能な状態にする」ことです。これらの言葉はそれぞれ少しずつ違う意味を持っています。状況に応じてこれらの言葉を正しく使い分けることで、仕組みを作る上でのそれぞれの段階の役割をより分かりやすく説明できます。それぞれの言葉の意味を正しく理解することは、より良い仕組み作りにつながるでしょう。
| 用語 | 意味 | 例 | 実装・導入・展開との関係 |
|---|---|---|---|
| 実装 | 仕組みを「使えるようにする」こと | 新しい会計処理ソフトウェアをインストールし、設定を行い、実際に使える状態にする | 導入の一部。展開を含む。 |
| 導入 | 仕組みを「使い始める」こと | 新しい会計処理ソフトウェアを会社に取り入れ、従業員に使い方を教え、運用を開始する | 実装を含む上位概念。展開を含む場合もある。 |
| 展開 | 仕組みを「利用可能な状態にする」こと | 新しい販売管理システムを全国の支店にインストールし、設定を行い、各支店が使える状態にする | 多くの場合、実装の一部として行われる。導入に含まれる場合もある。 |
