通信速度が遅い!?狭帯域の基礎知識

ITの初心者
先生、「狭帯域」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

ITアドバイザー
「狭帯域」は、データをやり取りする際の道の幅が狭いイメージだよ。道が狭いので、一度にたくさんのデータを送ることはできないんだ。

ITの初心者
なるほど。じゃあ、反対に広い場合はなんて言うんですか?

ITアドバイザー
それは「広帯域」と言うんだ。インターネットが速くなったと言われるのは、この「広帯域」の技術が進歩したからなんだよ。
狭帯域とは。
「コンピューターやインターネットで使う言葉で、『狭帯域』ってなんのこと?」
狭帯域とは
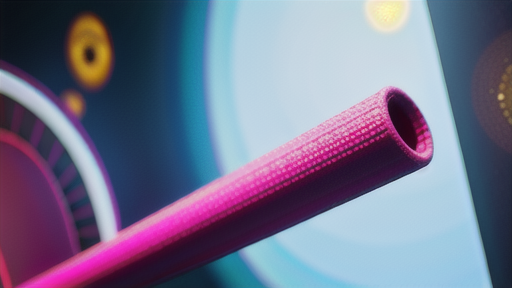
– 狭帯域とは「狭帯域」とは、データ通信において、限られた周波数帯域幅を使って情報を送受信する方式のことを指します。あるいは、その限られた帯域幅そのものを指す場合もあります。情報を送るための道筋をイメージしてみてください。広々とした高速道路では、一度にたくさんの車が行き交うことができますよね。データ通信でも、周波数帯域幅が広いほど、一度にたくさんのデータを送受信できます。これは、高速道路で一度に通行できる車の台数が多いのと同じイメージです。一方、狭帯域は、イメージとしては細い山道のようなもの。一度に通れる車の台数が限られてしまうように、一度に送受信できるデータ量が限られてしまい、通信速度が遅くなってしまうという特徴があります。しかし、狭帯域だからといって、常にデメリットがあるわけではありません。状況によっては、狭帯域は長距離の通信に適しているというメリットも持ち合わせています。これは、山道は整備されていれば遠くまでつながっていることが多いように、狭帯域は少ない電力で遠くまで電波を届けることができるためです。このように、狭帯域は通信速度が遅いという側面を持ちつつも、状況によっては有利に働く側面も持ち合わせています。そのため、一概に良し悪しを判断するのではなく、使用シーンに合わせて適切な通信方式を選ぶことが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 狭帯域とは | 限られた周波数帯域幅を使ったデータ通信方式 |
| イメージ | 細い山道 |
| 特徴 | 一度に送受信できるデータ量が限られ、通信速度が遅い |
| メリット | 少ない電力で遠くまで電波を届けることができるため、長距離通信に適している |
| デメリット | 通信速度が遅い |
| 結論 | 使用シーンに合わせて適切な通信方式を選ぶことが重要 |
狭帯域の特徴

– 狭帯域の特徴狭帯域は、広帯域に比べて通信速度が遅いという側面があります。しかし、電波が届く範囲が広く、消費電力が少ないという大きな利点があります。通信速度が遅くても問題ない用途では、狭帯域は非常に有効な通信方式です。例えば、山間部や離島など、広帯域の通信インフラを構築することが難しい地域では、狭帯域が活躍します。遠距離まで電波が届くという特性を生かし、広範囲をカバーする通信網を構築することができます。また、センサーやメーターなど、データの送信量が少ないIoTデバイスにも適しています。消費電力が少ないため、バッテリーの持ちが良く、長期間にわたって安定した通信を実現できます。このように、狭帯域は広帯域とは異なる特徴を持つ通信方式であり、用途に合わせて使い分けることで、より便利で快適な通信環境を実現することができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通信速度 | 遅い |
| 通信範囲 | 広い |
| 消費電力 | 少ない |
| メリット | ・電波が届く範囲が広い ・消費電力が少ない |
| デメリット | ・通信速度が遅い |
| 活用例 | ・山間部や離島など、広帯域の通信インフラ構築が難しい地域 ・センサーやメーターなど、データ送信量の少ないIoTデバイス |
狭帯域の利用例

– 狭帯域の利用例狭帯域は、データを送受信できる範囲が狭い代わりに、低電力で長距離通信を実現できるという特徴があります。そのため、従来から、大量のデータを送受信する必要がない分野で広く活用されてきました。例えば、FAXは、画像データを圧縮して送受信することで、狭帯域でも十分な品質を実現しています。また、工場やプラントなどで稼働状況を監視するテレメトリーシステムでは、センサーデータなど、少量のデータを定期的に送信する必要があるため、狭帯域が適しています。近年では、あらゆるモノがインターネットに接続されるIoT(モノのインターネット)の普及に伴い、狭帯域は再び脚光を浴びています。IoTでは、温度や湿度、照度などのセンサーデータなど、少量のデータを収集するケースが多く、狭帯域はうってつけの通信方式と言えるでしょう。特に、LPWA(Low Power Wide Area)と呼ばれる、低消費電力で広範囲をカバーできる狭帯域無線通信技術は、IoTの普及を支える重要な技術として期待されています。LPWAには、Sigfox、LoRaWAN、NB-IoTなど、様々な規格が存在し、用途や環境に応じて使い分けられています。このように、狭帯域は、従来の用途に加え、IoTをはじめとする新たな分野でも、その特性を生かして幅広く活用されていくことが予想されます。
| 特徴 | 用途 | 具体例 |
|---|---|---|
| データ送受信範囲が狭い | 大量のデータ送受信が必要ない分野 | FAX、テレメトリーシステム |
| 低電力で長距離通信が可能 | IoT(モノのインターネット) | センサーデータ収集 |
| 低消費電力、広範囲をカバー(LPWA) | IoTの普及を支える技術 | Sigfox、LoRaWAN、NB-IoT |
狭帯域と広帯域

– 狭帯域と広帯域「狭帯域」とは、限られた狭い周波数帯域を使って情報を送受信する通信方式のことです。 一方、「広帯域」とは、狭帯域よりもずっと広い周波数帯域を使うことで、より多くの情報を一度に送受信できる通信方式を指します。イメージとしては、細い管と太い管に例えることができます。 細い管に一度に通せる水の量は限られていますが、太い管であればより多くの水を一度に流すことができます。 これと同じように、通信においても、広い周波数帯域を使う広帯域の方が、一度にたくさんのデータを送受信できるのです。かつてインターネットの主流は狭帯域でしたが、動画配信やオンラインゲームなど、大量のデータを高速でやり取りする必要性が高まった現代では、広帯域が主流となっています。 広帯域は、大容量のデータをスムーズに送受信できるため、ストレスなくインターネットを楽しむことができます。 例えば、高画質・高音質の動画を途切れることなく視聴したり、オンラインゲームで快適にプレイしたりすることが可能です。
| 項目 | 狭帯域 | 広帯域 |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 狭い | 広い |
| データ伝送量 | 少ない | 多い |
| 速度 | 遅い | 速い |
| 例え | 細い管 | 太い管 |
| 用途 | かつてのインターネット主流 | 現代のインターネット主流、動画配信、オンラインゲームなど |
| メリット | – | 大容量データの送受信、ストレスのないインターネット利用 |
今後の狭帯域

これからの社会では、5Gやモノのインターネットの広がりによって、通信のあり方はますます多種多様になっていくと見られています。このような中、狭帯域は広帯域とは異なる特性を活かし、特定の用途において引き続き重要な役割を担っていくと考えられます。
狭帯域の最大のメリットは、広帯域と比べて電力消費が少ないという点です。この特徴は、電池で動くことが求められるモノのインターネット機器にとって、特に大きな魅力となります。例えば、広大な農地などに設置されたセンサーから、作物の状態に関するデータを集めて分析するといった用途では、長期間にわたって安定した通信を確保するために、低消費電力であることは非常に重要となります。
また、狭帯域は広帯域と比べて、電波が遠くまで届きやすい、障害物の影響を受けにくいといった特性も持っています。そのため、山間部や地下など、電波状況が厳しい場所でも、安定した通信を確立することができます。
このように、狭帯域は広帯域とは異なる強みを持つため、今後の通信環境においても、特定のニーズに対応する技術として、重要な役割を果たしていくことが期待されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 今後の通信のあり方 | 5Gやモノのインターネットの広がりによって多種多様になる |
| 狭帯域のメリット1 | 広帯域と比べて電力消費が少ないため、電池駆動の機器に適している |
| 狭帯域のメリット2 | 広帯域と比べて、電波が遠くまで届きやすく、障害物の影響を受けにくい |
| 狭帯域の活用例 | 広大な農地などに設置されたセンサーからのデータ収集など |
| 狭帯域の今後の役割 | 特定のニーズに対応する技術として重要 |
