Webアクセシビリティの要WCAGとは

ITの初心者
先生、『WCAG』って最近よく聞くんですけど、どういう意味ですか?

ITアドバイザー
良い質問だね!『WCAG』は、『ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン』の略で、ウェブサイトやウェブページを作る人が、誰でも見やすく、使いやすくするためのルールなんだ。

ITの初心者
誰でも見やすく、使いやすく…?具体的にはどんなルールがあるんですか?

ITアドバイザー
例えば、色の見分けにくい人にも分かりやすいように、色の組み合わせを工夫したり、キーボードだけでも操作できるようにしたり…といったことが挙げられるよ。
WCAGとは。
「IT用語の一つに『ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン』というものがあります。これは、ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアムという団体が作った、ウェブサイトを誰にとっても使いやすくするためのルールです。初めて作られたのは1999年で、2008年に新しいバージョンが発表されました。インターネットやそれに関連する技術は日々進化していますが、このルールは特定の環境や技術に左右されない基本的な考え方や指針を定めているため、長く使い続けることができます。なお、『ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン』は英語で『WebContentAccessibilityGuidelines』と書くため、それぞれの単語の頭文字を取って『WCAG』と略されることがあります。」
WCAGの概要

– WCAGの概要WCAGは「ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン」の略称で、ウェブページを含むウェブコンテンツを、誰もが利用しやすくするための基準です。具体的には、高齢者や障害者など、さまざまな能力を持つ人々がウェブコンテンツを閲覧したり、利用したりする際に、可能な限り支障をなくすことを目的としています。このガイドラインは、WWWコンソーシアム(W3C)という、ウェブ技術の標準化を進める国際的な団体によって作成されました。1999年に最初のバージョンが発表されて以来、技術の進歩や、利用者のニーズの変化に対応するため、何度か改訂が重ねられてきました。2008年には「WCAG 2.0」が、そして2018年にはモバイル端末の普及などを踏まえた「WCAG 2.1」が発表され、現在に至ります。WCAGは、ウェブコンテンツを「知覚できる」「操作できる」「理解できる」「堅牢である」という4つの原則に基づいて評価します。それぞれの原則には具体的な達成基準が設けられており、ウェブ制作者はこれらの基準を満たすことで、より多くの人が利用しやすいウェブサイトを作成することができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| WCAGの正式名称 | ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン |
| 目的 | 高齢者や障害者など、様々な能力を持つ人々がウェブコンテンツを閲覧・利用する際の支障をなくす |
| 作成団体 | W3C(ウェブ技術の標準化を進める国際的な団体) |
| バージョン履歴 | – 1999年:最初のバージョン発表 – 2008年:WCAG 2.0発表 – 2018年:WCAG 2.1発表(モバイル端末普及などに対応) |
| 4つの原則 | – 知覚できる – 操作できる – 理解できる – 堅牢である |
WCAGの4つの原則

– WCAGの4つの原則Webコンテンツを誰にとっても使いやすく、アクセスしやすくするためのガイドライン、WCAG。このガイドラインの中核となるのが「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢」という4つの原則です。それぞれの原則が、どのようなユーザーを想定し、どのような配慮を求めているのか詳しく見ていきましょう。-# 知覚可能「知覚可能」とは、視覚や聴覚に障害を持つユーザーでも、Webサイトで提供される情報を認識できるようにすることを指します。例えば、画像には代替テキストを提供することで、画面を読み上げソフトを利用するユーザーにも内容を理解できるようにします。動画コンテンツには字幕や音声解説を付けることで、聴覚に障害を持つユーザーもコンテンツを楽しめるように配慮する必要があります。-# 操作可能「操作可能」とは、身体的な制約を持つユーザーでも、Webサイトをスムーズに操作できるようにすることを指します。キーボードだけでサイトの全ての機能が操作できるようにしたり、マウス操作が困難なユーザーのために音声認識ソフトに対応したりするなど、様々な入力方法を考慮する必要があります。また、ページの遷移やボタンの配置を分かりやすくすることで、ユーザーが迷わずに目的の操作を行えるように配慮することも大切です。-# 理解可能「理解可能」とは、Webサイトに掲載されている情報を、ユーザーが容易に理解できるようにすることを指します。専門用語を避けて分かりやすい言葉で説明したり、文章を簡潔にまとめたりすることで、認知特性や学習障害を持つユーザーにも内容が伝わるように配慮します。また、サイトの構成を分かりやすくし、ナビゲーションを明確にすることで、ユーザーが迷わずに必要な情報を見つけられるようにすることも重要です。-# 堅牢「堅牢」とは、Webサイトが様々なブラウザや支援技術に対応し、常に正しく表示・動作することを指します。これは、将来登場する新しい技術にも対応できる柔軟性を確保することを意味します。Web標準に準拠したコードを使用することで、様々な環境でアクセスするユーザーに安定した利用体験を提供することができます。
| 原則 | 想定ユーザー | 配慮事項 |
|---|---|---|
| 知覚可能 | 視覚や聴覚に障害を持つユーザー 例:画面読み上げソフト利用者 |
– 画像に代替テキストを提供 – 動画に字幕や音声解説を提供 – 色だけでなく、形状やテクスチャでも情報を区別 |
| 操作可能 | 身体的な制約を持つユーザー 例:キーボードのみで操作するユーザー、音声認識ソフト利用者 |
– キーボードだけで操作可能にする – 音声認識ソフトへの対応 – 分かりやすいページ遷移、ボタン配置 |
| 理解可能 | 認知特性や学習障害を持つユーザー | – 専門用語を避ける – 文章を簡潔にする – 分かりやすいサイト構成、ナビゲーション |
| 堅牢 | 様々な環境(ブラウザ、支援技術)でアクセスするユーザー | – Web標準に準拠したコードを使用 – 新しい技術への対応 |
WCAGの重要性

– WCAGの重要性ウェブサイトやウェブアプリケーションは、今や私たちの生活に欠かせないものとなっています。しかし、視覚や聴覚、身体的な障害、あるいは加齢による衰えなどにより、すべての人が等しくこれらの情報にアクセスできているわけではありません。そこで重要となるのが、ウェブコンテンツをアクセシブルにするためのガイドラインであるWCAGです。WCAGに準拠することで、ウェブサイトやウェブアプリケーションは、障害者や高齢者を含む、より多くの人にとって使いやすいものになります。例えば、画像に代替テキストを付けることで、視覚障害のあるユーザーはスクリーンリーダーを使ってその内容を理解することができますし、キーボードだけで操作できるようにすることで、マウスの利用が困難なユーザーもウェブサイトを閲覧することが可能になります。このようなアクセシビリティの向上は、企業にとっても大きなメリットをもたらします。第一に、顧客層の拡大につながります。障害者や高齢者を含むすべての人にとって使いやすいウェブサイトは、より多くの人を顧客として取り込む可能性を秘めています。第二に、企業イメージの向上につながります。誰もが利用しやすいウェブサイトを構築することは、企業の社会的責任を果たす取り組みとして、顧客からの信頼や共感を高めることにつながります。さらに、近年では、ウェブアクセシビリティを義務付ける法律やガイドラインが世界各国で制定されつつあります。日本でも、ウェブサイトのアクセシビリティに関するJIS規格が制定されています。WCAGに準拠することで、このような法的要件を満たし、法的リスクを低減することにもつながります。以上のことから、WCAGに準拠することは、すべての人にとって使いやすいウェブサイトを構築するために、そして、企業としての責任を果たし、ビジネスを成長させるためにも、非常に重要であると言えます。
| WCAGの重要性 | 詳細 |
|---|---|
| すべての人が情報にアクセスできるようにする | 視覚、聴覚、身体的な障害、加齢による衰えなどに関わらず、すべての人がウェブサイトやウェブアプリケーションを利用できるようにする。 |
| アクセシビリティの向上によるメリット |
|
| 法的要件への準拠 | 世界各国でウェブアクセシビリティに関する法律やガイドラインが制定されている。WCAGに準拠することで、法的リスクを低減できる。 |
WCAGの適用範囲
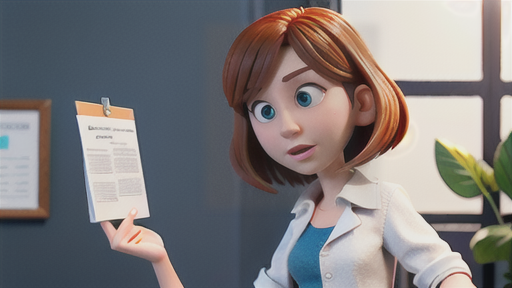
– WCAGの適用範囲
WCAG(ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン)は、ウェブサイトやウェブアプリケーション、ウェブコンテンツを開発、デザインするすべての人にとって、アクセシビリティを確保するための重要な指針です。
具体的には、ウェブデザイナーや開発者、コンテンツ制作者、プロジェクトマネージャーなど、ウェブサイト制作に関わる人すべてがWCAGについて理解を深め、アクセシビリティを考慮したウェブサイト制作を行う必要があります。
ウェブデザイナーは、色使いやコントラスト、フォントサイズ、レイアウトなどを検討する際、WCAGの基準を満たすようにデザインする必要があります。開発者は、ウェブサイトがスクリーンリーダーなどの支援技術に対応しているか、キーボード操作だけで利用できるかなどを確認しながら開発を進める必要があります。コンテンツ制作者は、画像に適切な代替テキストを付与したり、わかりやすい文章でコンテンツを作成したりするなど、誰もが理解しやすい情報発信を心がける必要があります。
プロジェクトマネージャーは、ウェブサイト制作の初期段階からアクセシビリティを考慮し、WCAGに準拠するための計画を立て、予算やスケジュールを調整する必要があります。また、制作チーム全体にアクセシビリティの重要性を周知し、WCAGの理解を深めるための研修などを実施することも重要です。
このように、WCAGはウェブサイト制作に関わるすべての人が理解し、実践すべき重要なガイドラインと言えるでしょう。
| 役割 | WCAGへの関わり |
|---|---|
| ウェブデザイナー | – 色使い、コントラスト、フォントサイズ、レイアウトをWCAG基準に沿って設計する |
| 開発者 | – スクリーンリーダーなどの支援技術への対応、キーボード操作の可否などを確認しながら開発 |
| コンテンツ制作者 | – 画像への代替テキスト付与、わかりやすい文章でのコンテンツ作成など、理解しやすい情報発信 |
| プロジェクトマネージャー | – アクセシビリティを考慮した計画、予算、スケジュールの調整 – チームへのアクセシビリティ重要性の周知、WCAG理解のための研修実施 |
WCAGのまとめ

WCAG(ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン)は、障害を持つ人を含め、誰もがウェブサイトを利用しやすくするための指針です。 ウェブサイトやウェブアプリケーション、ウェブコンテンツを制作する際に、このガイドラインに従うことで、より多くの人が情報やサービスにアクセスできるようになります。
WCAGは、視覚、聴覚、身体、認知など、さまざまな種類の障害に対応しており、ウェブサイトを誰にとっても使いやすいものにするために、具体的な達成基準を定めています。例えば、画像には代替テキストを提供することで、視覚障害を持つ人でも内容を理解できるようにする、あるいはキーボードだけで操作できるようにすることで、マウスが使えない人でもウェブサイトを閲覧できるようにする、といったことが求められます。
WCAGに準拠することで、企業や組織は、より多くの顧客を獲得し、社会的な責任を果たすことができます。また、法的観点からも、アクセシビリティへの配慮はますます重要になっています。
ウェブサイトのアクセシビリティを高めることは、私たち一人ひとりの課題です。WCAGを理解し、ウェブサイト制作やコンテンツ作成に携わる際には、積極的にアクセシビリティを考慮していくことが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| WCAGとは | 障害を持つ人を含め、誰もがウェブサイトを利用しやすくするための指針 |
| 目的 | ウェブサイトを誰にとっても使いやすいものにする |
| 対象 | 視覚、聴覚、身体、認知など、さまざまな種類の障害 |
| 具体的な達成基準 | 画像への代替テキスト提供、キーボードのみでの操作保証など |
| メリット | 顧客獲得、社会的責任を果たす、法的観点からの配慮 |
| 重要性 | ウェブサイト制作やコンテンツ作成に携わる際には、積極的にアクセシビリティを考慮していく |
