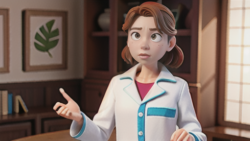デザイン
デザイン GUI:コンピュータをより身近にする技術
- GUIとは
GUIとは、「Graphical User Interface」を短くした言葉で、コンピュータの画面上に表示される絵や図形を使って、誰でも簡単に操作できるようにした仕組みのことです。
GUIが登場する前は、コンピュータに何か仕事をさせたい時、キーボードを使って複雑な命令文を入力する必要がありました。これはまるで、外国語を辞書で調べながら話しかけるように、とても難しく大変な作業でした。
しかし、GUIが登場したことで状況は一変しました。画面上に表示された分かりやすい絵や図形を選ぶだけで、コンピュータを操作できるようになったのです。例えば、ファイルを開きたい時は、ファイルの形をした絵をクリックするだけで済むようになりました。
このように、GUIは専門的な知識がない人でも、直感的にコンピュータを使えるようにした画期的な技術と言えるでしょう。今では、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなど、様々な機器でGUIが使われています。