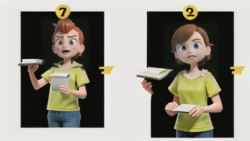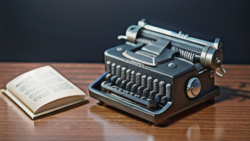開発
開発 リレーショナルデータベース管理システム:データ管理の基礎
- リレーショナルデータベース管理システムとは
現代社会において、企業や組織にとって情報は非常に重要な資産となっています。顧客情報、販売記録、在庫状況など、日々膨大な量のデータが発生し、蓄積されています。これらのデータを効率的に管理し、必要な時にすぐに取り出せるようにするためには、高性能なデータベースシステムが欠かせません。
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)は、まさにそのようなニーズに応えるために開発されたシステムです。
RDBMSは、データを「テーブル」と呼ばれる表の形で整理します。テーブルは、行と列から構成され、それぞれの行がデータの個々のレコードを表し、列がデータの種類を表します。例えば、顧客情報を管理する場合、「顧客ID」「氏名」「住所」「電話番号」といった項目を列として定義し、それぞれの顧客の情報を各行に格納していくイメージです。
RDBMSの最大の特徴は、複数のテーブル間を「関係」づけることができる点にあります。例えば、「顧客テーブル」と「注文テーブル」を「顧客ID」を共通のキーとして関連付けることで、ある顧客がどの商品を、いつ、いくつ注文したのかといった情報を簡単に抽出することができます。このように、データを関連付けて管理することで、必要な情報を効率的に検索したり、分析したりすることが可能になります。
RDBMSは、企業内の様々なシステムで広く利用されており、今日の情報化社会を支える重要な基盤技術となっています。