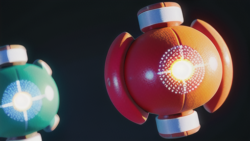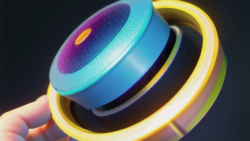開発
開発 照会言語:データベース活用への鍵
{情報を蓄積する箱のようなデータベースの中には、整理されたデータが大量にしまわれています。これらのデータの中から必要なものを探し出す、あるいは新しく付け加えたり、変更したりするために使うのが照会言語です。}
データベースは、会社での活動や研究など、様々な場面で情報の宝庫として使われています。この宝庫から必要な情報を取り出すためには、適切な指示が必要です。その指示を出すための手段が、まさに照会言語です。
図書館を例に考えてみましょう。図書館には数えきれないほどの本が所蔵されています。読みたい本を見つけるには、本の名前や作者、あるいは本のテーマといった情報を司書に伝えます。司書は伝えられた情報を元に、読みたい本を探し出してくれます。データベースにおける照会言語は、この司書への指示のような役割を果たします。
照会言語を使ってデータベースに指示を出すことで、必要な情報を取り出すことができます。例えば、顧客名簿の中から特定の地域に住む顧客の情報だけを抽出したり、商品の売上データから売れ筋商品を特定したりすることができます。また、新しい顧客情報を追加したり、既存の顧客情報を更新することも可能です。
照会言語はデータベース管理システム(DBMS)というソフトウェアの一部です。DBMSはデータベースの作成、管理、運用を行うためのソフトウェアであり、照会言語はその中でデータ操作の中核を担っています。照会言語を使いこなせるようになれば、データベースをより効率的に活用し、必要な情報を迅速に得ることが可能になります。 まさにデータベースという宝の山から宝石を掘り出すための、強力な道具と言えるでしょう。