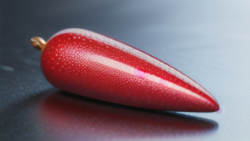デバイス
デバイス エンタメを持ち歩こう!PSPのスゴイ機能
2004年、ソニー・コンピュータエンタテインメントから、それまでの携帯ゲーム機の常識を覆す、全く新しい携帯ゲーム機が登場しました。その名は「プレイステーションポータブル」、通称PSPです。
PSPは、当時としては画期的であった高精細な液晶画面を搭載し、据え置き型ゲーム機に匹敵する美しいグラフィックを実現しました。ゲームファンは、その映像美に驚き、携帯ゲーム機の概念を大きく変えられました。
また、PSPの魅力はグラフィックだけにとどまりません。音楽や動画の再生、インターネット接続など、多彩な機能を備えており、まさに「オールインワン」のエンターテイメント機器として、多くのユーザーの心を掴みました。
さらに、メモリースティックDuoという記録媒体を採用したことで、ゲームデータの保存だけでなく、写真や音楽を持ち運ぶことも可能になりました。この革新的な機能により、PSPはゲーム機としての枠を超え、人々のライフスタイルに寄り添う存在へと進化していったのです。