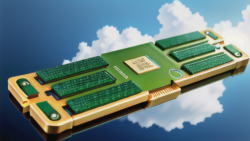ハードウエア
ハードウエア データ保存の基礎: 固定ディスクとは?
- 固定ディスクの役割固定ディスクは、コンピューターにとって重要な役割を担う、情報を保存しておくための装置です。 私たちが普段目にしているパソコンや、情報機器の中に入っていて、写真や音楽、動画、文書など、様々なデジタルデータはこの固定ディスクに保存されています。固定ディスクは、回転する円盤に情報を磁気によって記録する仕組みを持っています。 この仕組みのおかげで、コンピューターの電源を切っても情報は消えずに残り、長期にわたって情報を保管することができます。 情報を保存する場所である固定ディスクは、ちょうど図書館の書庫のような役割を果たします。たくさんの本が書庫に整理されて保管されているように、膨大な量のデジタルデータが固定ディスクに整理され保存されています。そして、私たちが必要な時に必要な情報をすぐに取り出せるように、コンピューターは固定ディスクにアクセスして情報を呼び出すことができます。このように固定ディスクは、私たちがデジタル情報を扱う上で欠かせない存在となっています。 日々利用するデータだけでなく、システムを動かすために必要なデータなども固定ディスクに保存されており、コンピューターが正常に動作するためには無くてはならない存在と言えるでしょう。