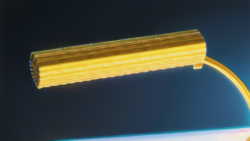ハードウエア
ハードウエア データの一時保管場所:揮発メモリー
- 揮発メモリーとは
揮発メモリーとは、電気が供給されている間のみ情報を記憶しておけるメモリーのことです。私たちの身の回りにあるコンピューターやスマートフォンといった電子機器には、ほぼ必ずと言っていいほど揮発メモリーが内蔵されています。
揮発メモリーは、機器が処理中のデータや動作に必要なプログラムを一時的に保存する場所として使われます。このメモリーの特徴は、データの読み書き速度が非常に速いという点にあります。そのため、CPUは揮発メモリーに置かれたデータにアクセスすることで、様々な処理を効率的に行うことができるのです。
しかし、揮発メモリーは電源を切ってしまうと記憶していた情報を失ってしまうという性質があります。そのため、重要なデータは、電源を切ってもデータが消えない不揮発メモリーに保存しておく必要があります。不揮発メモリーの代表例としては、ハードディスクやSSDなどが挙げられます。
揮発メモリーは、コンピューターの性能を左右する重要な要素の一つです。処理速度の速い揮発メモリーを搭載することで、快適に電子機器を使うことができます。