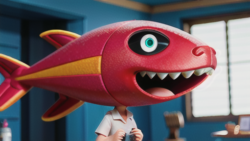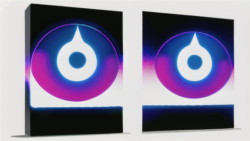ハードウエア
ハードウエア 現代社会の立役者:半導体集積回路
- 半導体集積回路とは
半導体集積回路は、一般的にはIC(アイシー)と呼ばれ、スマートフォンやパソコン、テレビ、冷蔵庫といった、私たちの身の回りのあらゆる電子機器に搭載されている、現代社会に欠かせない電子部品です。 このICは、トランジスタや抵抗、コンデンサといった電子部品を、髪の毛よりもはるかに小さい半導体チップの上に、極めて高い密度で集積して作られています。
半導体チップは、主にシリコンという元素を材料としており、その表面に複雑な回路パターンを形成することで、様々な機能を実現します。この回路パターンは、ちょうど都市の地図のように精巧に設計されており、電気信号を制御することで、計算や記憶、信号の増幅など、電子機器に必要な様々な処理を行います。
ICの特徴は、その集積度の高さにあります。近年、微細加工技術の進歩により、1つのチップ上に数十億個ものトランジスタを集積することが可能となり、ICの性能は飛躍的に向上しました。同時に、ICの小型化も進み、電子機器全体の小型化、軽量化にも大きく貢献しています。
このように、半導体集積回路は、小型化、高性能化、低価格化を実現する上で欠かせない技術であり、私たちの生活をより便利で豊かにする原動力となっています。