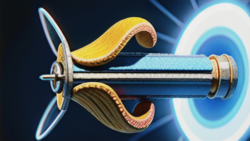ハードウエア
ハードウエア システム終了:安全な電源オフ
計算機を安全に止めて、その後電源を落とす一連の作業を、計算機終了と言います。ただ電源のつまみを押して無理やり電源を切るのではなく、計算機終了の手順を踏むことが大切です。そうすることで、情報の紛失や計算機の故障を防ぐことができます。
計算機の頭脳である基本ソフトは、計算機終了の指示を受け取ると、動いている様々な道具をきちんと終わらせます。まだしまわれていない情報をしまうように促し、記憶装置への書き込み作業を終えてから、電源を切ります。これは、突然の電源断によって情報が壊れたり、計算機の大切な仕組みが壊れたりするのを防ぐために、とても大切なことです。
例えば、文章を書いている途中で急に電源が切れてしまうと、書いていた内容が消えてしまうかもしれません。計算機終了の手順を踏めば、基本ソフトが「情報を保存しますか?」と聞いてくれるので、作業内容を失わずに済みます。また、計算機の内側では、様々な道具が動いています。これらの道具は、記憶装置にある様々な情報を読み書きしながら仕事をしています。急に電源を切ってしまうと、これらの情報が壊れてしまい、計算機が正常に動かなくなる可能性があります。計算機終了の手順を踏むことで、基本ソフトがこれらの道具を安全に止め、情報をきちんと保存してから電源を切るため、計算機を安全に守ることができるのです。
計算機終了は、普段使っている卓上の計算機だけでなく、多くの情報を管理する大型計算機や、その他の電子機器でも大切な作業です。適切な手順で計算機を終了することで、大切な情報を守り、計算機を長く使うことができます。