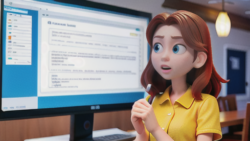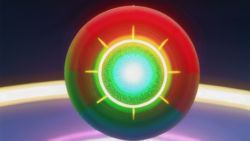インフラ
インフラ データセンター:情報時代の心臓部
情報社会を支える重要な施設、それが情報処理センターです。情報処理センターとは、たくさんの計算機や通信機器、情報を保存する装置などを設置し、それらを安定して動かし続けるための建物のことです。現代の暮らしに欠かせないインターネットや、情報をインターネット上で共有する仕組み、インターネットを通して遊ぶゲームなどは、全て情報処理センターによって支えられています。これらの仕組みは、非常にたくさんの情報を処理し、いつでも利用できるようにしておく必要があります。まさに情報時代の心臓部と言えるでしょう。
情報処理センターは、災害や停電といった緊急事態にも対応できるようになっています。堅牢な安全対策や、機器が故障してもすぐに別の機器で代わりを担える仕組みが備えられています。建物全体を一つの巨大な計算機と考えることもできるでしょう。その内部では、数え切れないほどの機械が休むことなく動き続け、情報を処理しています。
情報処理センターの内部は、常に適切な温度や湿度に保たれています。計算機は熱に弱いため、冷房装置を使って温度を一定に保つ必要があります。また、湿度が高すぎると機器が故障する原因となるため、除湿装置も稼働しています。さらに、停電に備えて自家発電装置なども設置されています。これらの設備によって、情報処理センターは24時間365日、安定した稼働を続けることができるのです。
情報処理センターは、私たちの生活を支える重要な社会基盤の一つと言えるでしょう。これからも情報処理センターは進化を続け、より便利で豊かな情報社会の実現に貢献していくことでしょう。