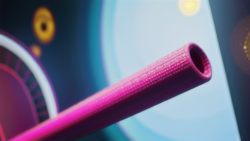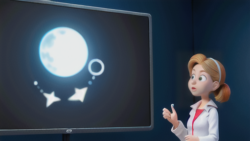ネットワーク
ネットワーク ネットワークの縁の下の力持ち: リピータ
- リピータとはコンピュータなどの機器がネットワークを通じて情報をやり取りする際、電気信号や光信号を使ってデータを送受信しています。しかし、これらの信号は長い距離を送信するうちに次第に弱くなってしまうという性質があります。これが「信号減衰」と呼ばれる現象です。遠くまで情報を正確に伝えるためには、この信号減衰を克服する必要があります。そこで活躍するのが「リピータ」です。リピータは、弱くなった信号を受信し、その信号を増幅して再び送信することで、信号減衰の問題を解決する役割を担います。言わば、ネットワーク上の中継地点として機能し、遠くまで情報を伝えるための橋渡し役を担っているのです。リピータは、信号の内容を理解したり、変更したりすることはありません。あくまで、受信した信号をそのままの形で増幅して送り出すだけのシンプルな仕組みです。しかし、このシンプルな仕組みこそが、広範囲なネットワークを構築する上で非常に重要な役割を果たしているのです。リピータの導入により、企業内ネットワークやインターネットなど、様々なネットワークにおいて、より広範囲にわたって安定した通信が可能となっています。