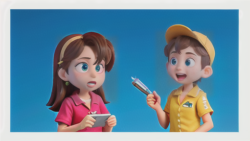セキュリティ
セキュリティ デジタル署名:インターネット上の信頼を守る技術
- デジタル署名とは
デジタル署名は、インターネット上でやり取りされるデータが、送信者本人によって作成され、かつ送信後に改竄されていないことを証明する技術です。
紙の文書に印鑑を押して、その文書の正当性を保証するように、デジタルデータにも電子的な印鑑を押すことで、データの信頼性を確保します。この電子的な印鑑こそが、デジタル署名です。
デジタル署名は、「公開鍵暗号」と呼ばれる高度な数学的技術を応用して実現されています。公開鍵暗号では、署名を作成する「秘密鍵」と、署名を検証する「公開鍵」の2つの鍵がペアで用いられます。
送信者は、自分だけが持つ秘密鍵を使ってデジタル署名を作成し、データに添付して送信します。受信者は、送信者から公開されている公開鍵を使って署名を検証することで、データが本当に送信者本人によって作成され、改竄されていないことを確認できます。
デジタル署名は、電子署名とも呼ばれ、電子契約や電子申請など、様々な場面で活用されています。