多くの環境で動くアプリを作る技術

ITの初心者
先生、「多くの機械で動く」って意味のマルチプラットフォームって、どういうことですか?

ITアドバイザー
いい質問だね!パソコンやスマホ、ゲーム機など、いろいろな種類の機械で同じように動く仕組みのことだよ。例えば、あるゲームがパソコンでもスマホでも遊べたら、それはマルチプラットフォームだね。

ITの初心者
なるほど!種類が違う機械でも、同じように動くように作るのは大変じゃないですか?

ITアドバイザー
確かに、それぞれの機械の仕組みを理解して作らないといけないから、大変な部分もあるね。でも、一度作ってしまえば、たくさんの人に使ってもらえるから、開発するかいはあるんだよ。
multi-platformとは。
情報技術の用語で、『様々な種類の機器で使える』という意味を持つ『マルチプラットフォーム』(別の言い方で『クロスプラットフォーム』とも言う)について。
様々な機器で使えるアプリ

近ごろ、携帯電話や机上計算機、書き込み式計算機など、様々な機器が広く使われるようになりました。これらの機器で共通して使える応用を組み立てる技術のことを、多くの台に対応した開発と言います。一つの仕組みで様々な種類の機器に対応できるため、開発費用の切り詰めや開発時間の縮まりに繋がります。また、使う人にとっても、どの機器でも同じように応用を使えるという良い点があります。例えば、通勤電車では携帯電話で遊びの続きを行い、自宅では机上計算機のでかい画面で同じ遊びを楽しむことができます。
多くの台に対応した開発には、様々な方法があります。よく使われる方法の一つに、応用を動かすための特別な場所を作る方法があります。この方法では、それぞれの機器向けに合わせた小さな部品を用意するだけで済みます。このため、開発の手間を大きく減らすことができます。もう一つの方法として、機械の言葉に置き換える作業をそれぞれの機器ごとに行う方法があります。この方法は、機器の持つ力を最大限に引き出すことができますが、それぞれの機器に合わせた仕組みを作る必要があるため、手間がかかります。
多くの台に対応した開発は、様々な環境でも同じように動く応用を提供するための大切な技術です。開発の手間を減らし、使う人にとって使いやすい応用を作るために、これからも様々な技術が開発されていくでしょう。技術の進歩によって、さらに多くの機器で同じ応用が使えるようになる未来が期待されます。また、多くの台に対応した開発は、様々な機器を使う機会が増える中で、ますます重要性を増していくと考えられます。
| メリット | デメリット | 手法 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 開発費用削減、開発時間短縮、ユーザーの利便性向上 | – | クロスプラットフォーム開発 | 様々な機器で同じアプリケーションを使用できるようにする技術 |
| 開発の手間を大きく削減 | – | 仮想マシン方式 | アプリケーション実行のための専用環境を用意し、各機器向けに小さな部品を用意 |
| 機器の性能を最大限に活用 | 手間がかかる | ネイティブコンパイル方式 | 各機器の機械語に翻訳するため、個別に開発が必要 |
マルチプラットフォーム開発の利点

近頃、様々な機器に対応したアプリ開発が求められています。携帯電話、平板型端末、携帯用音楽プレーヤーなど、種類も性能も多様な機器に対応するために、マルチプラットフォーム開発という手法が注目を集めています。この手法は、一つのプログラムで複数の機器に対応できるため、従来の方法に比べて多くの利点があります。
まず、開発にかかる時間と費用を大幅に抑えることができます。従来は、それぞれの機器に合わせて個別にプログラムを作成する必要がありました。例えば、携帯電話向けと平板型端末向けにアプリを開発する場合、それぞれ専用のプログラムを別々に作る必要があったのです。しかし、マルチプラットフォーム開発では、一つのプログラムで両方の機器に対応できます。そのため、開発時間を短縮し、費用も抑えることが可能になります。これは、開発側にとって大きなメリットと言えるでしょう。
次に、プログラムの維持管理を効率化できます。複数のプログラムを管理するよりも、一つのプログラムを管理する方がはるかに簡単です。不具合の修正や機能の追加など、プログラムの更新作業を一元管理できるため、作業効率が向上します。また、複数の機器で同じプログラムが動作するため、不具合の発生率を低く抑えることにもつながります。
さらに、利用者の満足度向上にも貢献します。どの機器を使っても同じ操作方法でアプリを利用できるため、利用者は戸惑うことなく快適にアプリを利用できます。機器が変わっても使い勝手に変化がないため、利用者の満足度向上につながるのです。
このように、マルチプラットフォーム開発は、開発者と利用者の双方にとって多くのメリットをもたらす、これからのアプリ開発に欠かせない手法と言えるでしょう。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 開発コストの削減 | 一つのプログラムで複数の機器に対応できるため、開発時間と費用を大幅に削減できます。 |
| 維持管理の効率化 | プログラムの一元管理により、更新作業が効率化され、不具合発生率も低くなります。 |
| 利用者満足度の向上 | どの機器でも同じ操作方法で利用できるため、快適な操作性を実現し、満足度向上に貢献します。 |
マルチプラットフォーム開発の種類

様々な機器で動く仕組みを作ることを、マルチプラットフォーム開発と言います。この開発には色々なやり方があり、それぞれに長所と短所があります。開発するものの特徴や開発する側の体制を考えて、最適な方法を選ぶことが大切です。代表的な方法として、インターネットで使われる技術を使った開発、交差翻訳を使った開発、仮想の機械を使った開発などがあります。
インターネットで使われる技術を使った開発では、ホームページ作成などに使われる技術を用いて仕組みを作ります。これらの技術は、パソコン、スマートフォン、タブレットなど、多くの機器で使えるため、広い範囲の機器に対応した仕組みを作ることができます。例えば、一つのプログラムを書くだけで、パソコンでもスマホでも使えるようにできるのです。しかし、機器特有の機能を使うのが難しい場合があります。高度な処理をするゲームなどには不向きです。
交差翻訳を使った開発では、プログラムを一度作れば、異なる機器向けに翻訳することで、それぞれの機器で動くようにできます。これは、まるで色々な国の言葉に翻訳するようなものです。この方法では、機器の性能を最大限に引き出すことができます。複雑なゲームや処理速度が求められるアプリに向いています。しかし、それぞれの機器向けに翻訳作業が必要になるため、手間がかかる場合があります。
仮想の機械を使った開発では、仮想の機械の上で動くプログラムを作ることで、様々な機器で動かすことができます。これは、どんな場所でも使える共通の入れ物を作って、その中にプログラムを入れるようなイメージです。この方法を使うと、一度プログラムを作れば、様々な機器で動かすことができます。しかし、仮想の機械を使うため、直接機器を操作するのに比べて処理速度が遅くなることがあります。
このように、マルチプラットフォーム開発には様々な種類があり、それぞれに利点と欠点があります。どの方法を選ぶかは、開発するものの目的や使える技術、開発にかかる時間や費用などを考えて決める必要があります。最適な方法を選ぶことで、効率的に開発を進めることができます。
| 開発方法 | 説明 | 長所 | 短所 | 向き・不向き |
|---|---|---|---|---|
| インターネット技術を使った開発 | ホームページ作成などに使われる技術を用いて仕組みを作る。 | 多くの機器で使えるため、広い範囲の機器に対応できる。 | 機器特有の機能を使うのが難しい。 | 高度な処理をするゲームなどには不向き。Webアプリなどに最適。 |
| 交差翻訳を使った開発 | 一度作ったプログラムを異なる機器向けに翻訳することで、それぞれの機器で動くようにする。 | 機器の性能を最大限に引き出すことができる。 | それぞれの機器向けに翻訳作業が必要になるため、手間がかかる。 | 複雑なゲームや処理速度が求められるアプリに向いている。 |
| 仮想の機械を使った開発 | 仮想の機械の上で動くプログラムを作る。 | 一度プログラムを作れば、様々な機器で動かすことができる。 | 仮想の機械を使うため、直接機器を操作するのに比べて処理速度が遅くなる。 | 処理速度が重要でないアプリに最適。 |
課題と将来展望

近年の情報技術の進歩は目覚ましく、様々な機器が広く使われるようになりました。これらの機器で共通して使えるアプリを作る手法、すなわち多くの場所で使えるアプリ作りは多くの利点を持つと同時に、いくつかの難題も抱えています。
まず、機器ごとの性能の差が挙げられます。処理速度の速い機器や遅い機器、使える記憶容量の多い機器や少ない機器など、様々な機器に対応しようとすると、それぞれの機器に合わせて調整する手間が生じます。例えば、高性能の機器では動画を滑らかに再生できても、低性能の機器ではカクカクしてしまうかもしれません。このような事態を防ぐには、性能の低い機器でも問題なく動くよう、画質を調整したり、処理を軽くしたりするなどの工夫が必要です。
次に、機器ごとの機能の差も課題となります。ある機器にはカメラが付いているけれど、別の機器には付いていない、といった違いです。カメラ機能を使ったアプリを作る場合、カメラのない機器では別の方法で代用する必要があります。機器によって使える機能が違うため、全ての機器で同じようにアプリを動かすには、それぞれの機能の有無を考慮した設計が欠かせません。
さらに、それぞれの機器の仕組みをよく理解していないと、アプリの動きが遅くなったり、 unexpectedな誤作動が起きたりする危険性があります。それぞれの機器に適した作り方を理解していないと、本来の性能を発揮できないだけでなく、思わぬ不具合を引き起こす可能性もあるのです。
しかし、技術の進歩は日進月歩であり、これらの難題も少しずつ解決されつつあります。様々な機器で共通して使えるようにする技術も進化しており、以前は難しかったことも、今では簡単にできるようになっています。
これから先、もっと多くの機器が普及し、機器同士が繋がることで、多くの場所で使えるアプリ作りの重要性はさらに高まっていくでしょう。より使いやすく質の高いアプリを作るために、これからも技術の進歩に注目していく必要があります。多くの場所で使えるアプリは、私たちの生活をより便利で豊かにしてくれる可能性を秘めているのです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 機器ごとの性能差 | 処理速度、記憶容量の違いにより、機器ごとに調整が必要。例えば、低性能機器では画質調整などが必要。 |
| 機器ごとの機能差 | カメラの有無など、機器によって使える機能が異なる。全ての機器で同じようにアプリを動かすには、機能の有無を考慮した設計が必要。 |
| 機器の仕組みの理解不足 | アプリの動作が遅くなったり、予期せぬ誤作動を起こす可能性がある。 |
| 技術の進歩 | 様々な機器で共通して使えるようにする技術も進化しており、以前は難しかったことも、今では簡単にできるようになっている。 |
| 将来展望 | 多くの機器が普及し、機器同士が繋がることで、多くの場所で使えるアプリ作りの重要性はさらに高まる。 |
まとめ
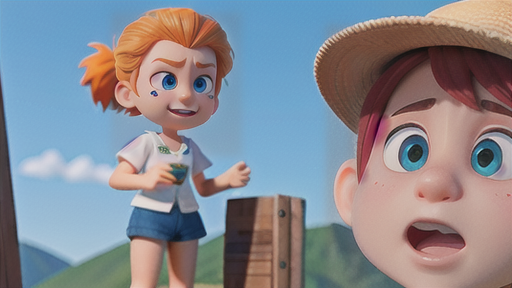
近年の情報技術の進歩は目覚しく、様々な携帯端末や計算機が登場しています。これらの機器で共通して使える応用ソフトを作ることは、開発側から見ても利用者側から見ても大きな利点があります。そこで注目されているのが、様々な機器に対応した応用ソフトを効率よく作るための技術、すなわち多くの機器に対応できる開発手法です。この手法を使うことで、一つ作った応用ソフトを様々な機器で動かすことができるため、開発にかかる費用と時間を大幅に減らすことができます。また、利用者にとってはどの機器でも同じように使えるため、とても便利です。
多くの機器に対応できる開発手法には、大きく分けて三つの方法があります。一つ目は、誰でも使える情報の表示ややり取りをするための技術を使う方法です。この技術を使うと、機器の種類に関係なく、共通の仕組みで応用ソフトを作ることができます。二つ目は、ある機器専用の応用ソフトを、別の種類の機器でも動くように変換する技術を使う方法です。これは、変換作業が必要ですが、それぞれの機器に最適な形に調整できるという利点があります。三つ目は、仮想的な計算機を作り、その上で応用ソフトを動かす方法です。この方法は、仮想的な計算機を作る手間はかかりますが、一度作ってしまえば様々な機器で同じように動かすことができます。
どの方法を選ぶかは、作る応用ソフトの種類や開発する側の体制によって異なります。例えば、簡単な機能の応用ソフトであれば、誰でも使える情報の表示ややり取りをするための技術を使うのが簡単です。一方、複雑な機能を持つ応用ソフトの場合は、それぞれの機器に最適な形に調整できる変換技術が適しているでしょう。また、開発チームの技術力や開発期間も考慮する必要があります。
今後、様々な機器に対応できる応用ソフトの需要はますます高まると考えられます。開発に携わる者にとって、多くの機器に対応できる開発手法を理解し、使いこなせるようにすることは、なくてはならない能力となるでしょう。この技術は常に進歩しており、これからもより多くの利用者に快適な使い心地を提供していく上で、重要な役割を果たすことは間違いありません。
| 開発手法 | 説明 | 利点 | 欠点/注意点 | 適した状況 |
|---|---|---|---|---|
| 共通の情報表示・やり取り技術 | 機器の種類に関係なく、共通の仕組みで応用ソフトを作る。 | 開発が容易。 | 複雑な機能の実装は難しい場合も。 | 簡単な機能の応用ソフト |
| 機器専用ソフト変換技術 | ある機器専用の応用ソフトを、別の種類の機器でも動くように変換する。 | それぞれの機器に最適な形に調整できる。 | 変換作業が必要。 | 複雑な機能を持つ応用ソフト |
| 仮想計算機利用技術 | 仮想的な計算機上で応用ソフトを動かす。 | 一度作れば様々な機器で同じように動く。 | 仮想的な計算機を作る手間がかかる。 | 開発チームの技術力が高い場合、開発期間が十分にある場合 |
