Macのファイル管理の仕組み HFSとは

ITの初心者
先生、「HFS」って聞いたことあるんですけど、どんなものなんですか?

ITアドバイザー
「HFS」は、アップルのコンピューター「Mac」で使われているファイルシステムだよ。ファイルの整理整頓の仕方のルールみたいなものだね。

ITの初心者
ファイルの整理整頓ですか?

ITアドバイザー
そうだよ。例えば、本棚に色々な本をしまう時に、小説はこっち、漫画はあっち、と決めておくと探しやすいよね。HFSはコンピューターの中でファイルを整理整頓して、必要な時にすぐ取り出せるようにしてくれるんだ。
HFSとは。
「HFS」という用語について説明します。「HFS」は、アップルのパソコン「Mac」で使われている基本ソフト「MacOS」で使われている、ファイルを整理するための仕組みです。1985年に初めて登場しました。その後、1998年に「HFS+(プラス)」という新しい仕組みに変わりましたが、最新の「MacOSX」でも「HFS+」は使われています。また、アップルの音楽プレーヤー「iPod」でも、ファイルの整理に「HFS」が使われています。「HFS」は、「Hierarchical File System」(階層化ファイルシステム)のそれぞれの単語の最初の文字をとったものです。
HFSとは

– HFSとはHFSは、「階層型ファイルシステム」を意味する”Hierarchical File System”の略称で、アップルが開発したファイルシステムです。ファイルシステムとは、コンピューター内のデータを整理し、アプリケーションソフトなどがデータにアクセスする際に利用する仕組みのことです。ハードディスクやSSDといった記憶装置は、このファイルシステムによって管理され、私たちがファイルやフォルダーとして認識できるようになっています。
HFSは、1985年に登場したMacintoshコンピュータのために設計されました。それまでMacintoshで使用されていたファイルシステムと比較して、HFSはより多くのファイルやフォルダーを管理できるようになり、ファイルへアクセスする速度も向上しました。この進化により、当時としては画期的だったグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を備えたMacintoshの操作性を支える重要な役割を担いました。
しかし、時代の流れとともにハードディスクは大容量化し、ファイルシステムにも更なる進化が求められるようになりました。そこで、HFSの後継として開発されたのがHFS Plus(HFS+)です。現在では、HFSに代わってHFS+がMacの標準ファイルシステムとして広く利用されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HFS | – 階層型ファイルシステム(Hierarchical File System)の略称 – アップルが開発したファイルシステム – 1985年に登場したMacintoshコンピュータのために設計 – 当時のMacintoshのGUIを支える重要な役割を担った |
| ファイルシステム | – コンピューター内のデータを整理し、アプリケーションソフトなどがデータにアクセスする際に利用する仕組み – ハードディスクやSSDといった記憶装置は、ファイルシステムによって管理 |
| HFS Plus (HFS+) | – HFSの後継として開発されたファイルシステム – 現在、Macの標準ファイルシステムとして広く利用 |
HFSの特徴
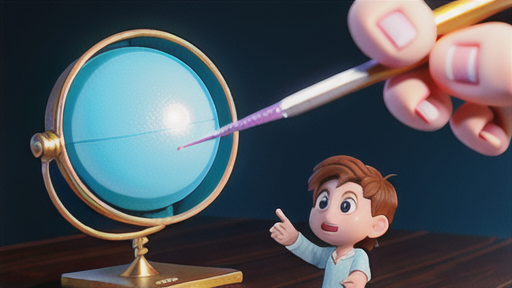
– HFSの特徴HFS(階層型ファイルシステム)は、その名の通り、ファイルを階層構造で管理する仕組みです。これは、まるで木構造のように、ルートディレクトリと呼ばれる起点となる場所に、複数のフォルダ(ディレクトリ)が枝分かれし、その中にさらにフォルダやファイルが格納されるという構造です。HFSの大きな特徴は、この階層構造を採用することで、ファイルを整理しやすくなる点です。例えば、写真、音楽、文書といった具合にカテゴリ分けしたフォルダを作成し、その中に関連するファイルを格納することで、目的のファイルを簡単に見つけることができます。また、HFSは日本語環境での利用にも適していました。ファイル名に最大31文字の日本語を付けることができたため、ファイルの内容を分かりやすく表現することが可能でした。これは、当時の多くのファイルシステムが日本語に対応していなかったことを考えると、画期的なことでした。これらの特徴から、HFSは長い間、Macintoshの標準ファイルシステムとして広く普及しました。しかし、時代の流れとともに、より大容量のストレージや、より多くのファイルに対応できるファイルシステムが必要とされるようになり、HFSに代わる新しいファイルシステムが登場しました。とはいえ、HFSの基本的な考え方は、現在のファイルシステムにも受け継がれています。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 階層構造 | ルートディレクトリを起点に、フォルダ(ディレクトリ)が木構造のように枝分かれし、ファイルが格納される。 |
| ファイルの整理のしやすさ | カテゴリ分けしたフォルダを作成することで、目的のファイルを簡単に見つけることができる。 |
| 日本語対応 | ファイル名に最大31文字の日本語を付けることが可能。 |
HFS Plus (HFS+) の登場

– HFS Plus (HFS+) の登場
1998年、それまでMacintoshで使われていた階層ファイルシステム(HFS)に、いくつかの改良を加えたHFS Plus (HFS+)が登場しました。この新しいファイルシステムは、当時の技術の進歩に合わせて開発され、より多くのデータを扱えるように設計されました。
HFS+の大きな特徴の一つに、ファイルサイズやハードディスク容量の増加に対応したことが挙げられます。従来のHFSでは扱うことのできなかった、より大きなサイズのファイルやハードディスクを管理できるようになったため、より多くの情報をパソコンに保存することが可能になりました。
また、ファイル名の長さに制限があったHFSと異なり、HFS+では最大255文字までのファイル名を扱えるようになりました。これにより、より長くわかりやすいファイル名を付けることができるようになり、ファイル管理の効率が向上しました。
さらに、HFS+ではファイルへのアクセス権限を設定する機能が追加されました。この機能により、ファイルへのアクセスを制限することができるようになり、より安全性の高いファイル管理が可能になりました。
これらの改良により、HFS+はMac OS 8.1以降のMacintoshにおいて標準のファイルシステムとして採用されました。その後も長年にわたりMacの主要なファイルシステムとして使用され続け、現在でも多くのMacで使用されています。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| ファイルサイズ/容量 | より大きなファイルサイズとハードディスク容量に対応 |
| ファイル名 | 最大255文字までのファイル名をサポート |
| アクセス権限 | ファイルへのアクセス権限を設定可能 |
| 採用OS | Mac OS 8.1以降 |
MacOSX以降も利用可能

Macintoshの次世代OSであるMac OS Xが登場した後も、ファイルシステムであるHFS+は、その役割を担い続けました。Mac OS Xは、UNIXという異なる基盤を採用しながらも、従来のMacintoshが採用していたHFS+との連携を保つことで、これまでの利用者が違和感なく移行できるよう配慮しました。
Mac OS Xの登場は、HFS+にとっても大きな転換期となりました。Mac OS Xの設計思想に基づき、HFS+はより堅牢性を増し、信頼性の高いファイルシステムへと進化を遂げました。これにより、Mac OS Xは、従来のMacintoshの使いやすさを継承しながら、より安定した動作環境を提供することに成功しました。
HFS+は、Mac OS Xの進化と共に歩み続け、長年にわたりMacの主要なファイルシステムとしての地位を確立しました。これは、HFS+がMacの進化に柔軟に対応してきたこと、そして、AppleがOSの移行において、ユーザーの利便性を重視してきたことの証と言えるでしょう。
| OS | ファイルシステム | 特徴 |
|---|---|---|
| Macintosh | HFS+ | 従来からのファイルシステム |
| Mac OS X | HFS+ | UNIXベース 従来のMacintoshとの連携を維持 堅牢性と信頼性の向上 |
iPodシリーズでの採用

– iPodシリーズでの採用2001年に登場し、世界中で大流行となったアップルの携帯音楽プレーヤー、iPod。その発売当初から採用されたファイルシステムこそ、HFSでした。Macintoshコンピュータで実績のあるHFSは、iPodの特性とも見事に合致していたのです。当時としては画期的だったiPodの大容量ストレージ。そこに、数千曲にも及ぶ音楽ファイルをユーザーは保存したいと望んでいました。HFSは、膨大な数のファイルを効率的に管理することに長けており、iPodの限られた容量を最大限に活用することが可能だったのです。さらに、HFSはファイルの断片化にも強いという特性を持っていました。音楽ファイルのように、比較的大きなサイズのファイルを扱うiPodにとって、断片化は処理速度の低下に繋がります。HFSは断片化を抑え、安定した再生を実現する上で最適な選択だったと言えるでしょう。このように、HFSはiPodの誕生と普及を陰ながら支え、世界中の人々に音楽を持ち歩く喜びを提供する一翼を担っていました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品 | iPod (初代) |
| 発売年 | 2001年 |
| ファイルシステム | HFS |
| HFS採用の理由 | – 当時としては画期的だったiPodの大容量ストレージに、数千曲にも及ぶ音楽ファイルを効率的に管理するため。 – ファイルの断片化に強く、音楽ファイルのように比較的大きなサイズのファイルを扱うiPodにとって、処理速度の低下を抑え、安定した再生を実現するため。 |
HFSの功績

階層ファイルシステム(HFS)は、1985年にアップル社が開発したファイルシステムで、それまでのMacintoshで使用されていたMacintosh File System (MFS) の後 successor として登場しました。HFSは、MFSが抱えていたファイル管理の限界を克服し、より多くのファイルやフォルダを効率的に扱うことができるよう設計されました。
HFSの大きな特徴の一つに、日本語ファイル名への対応が挙げられます。これは、当時のパーソナルコンピュータのファイルシステムとしては画期的なことで、日本のユーザーが容易にMacintoshを利用できる環境を整え、その後のMacintoshの普及を大きく後押ししました。
HFSは、その登場から長年にわたり、Macintosh標準のファイルシステムとして利用されてきましたが、時代の流れとともに、より高度な機能を備えたファイルシステムが求められるようになりました。その結果、HFSは、後継となるHFS Plus (HFS+) にその座を譲ることになりました。HFS+は、HFSの基本的な構造を継承しつつ、より大容量のストレージに対応し、ファイルのアクセス速度やセキュリティ面などが強化されています。
現在では、HFSは、HFS+やAPFS (Apple File System) といった新しいファイルシステムに取って代わられましたが、Macintoshの歴史において重要な役割を果たしたファイルシステムとして、その功績は高く評価されています。HFSの登場は、単にファイルシステムの進化にとどまらず、日本のコンピュータの普及にも大きく貢献した出来事と言えるでしょう。
| ファイルシステム | 特徴 | 開発年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| MFS (Macintosh File System) | – | – | HFSの前身 |
| HFS (Hierarchical File System) | – MFSの限界を克服 – より多くのファイルやフォルダを効率的に処理 – 日本語ファイル名に対応 |
1985年 | – 長年Macintosh標準のファイルシステムとして利用 – 後 successor HFS+ にその座を譲る |
| HFS+ (HFS Plus) | – HFSの基本構造を継承 – より大容量のストレージに対応 – ファイルのアクセス速度やセキュリティ面などが強化 |
– | – HFSの後継 |
| APFS (Apple File System) | – | – | – HFS+の後 successor |
