複数画面で作業効率アップ!マルチモニターのススメ

ITの初心者
先生、『マルチモニター』って、複数の画面を使うことですよね?どういう時に役立つのでしょうか?

ITアドバイザー
そうだね。複数の画面を使うことだよ。同時に複数の作業をする際に役立つんだ。例えば、片方の画面で資料を見ながら、もう片方の画面で文章を作成する、といった使い方だね。

ITの初心者
なるほど。資料を見ながら作業できるのは便利そうですね。他にはどんな使い方がありますか?

ITアドバイザー
例えば、大きな表計算ソフトのデータ全体を見やすく表示したり、動画編集ソフトで複数の動画の編集状況を同時に確認したり、プログラミングで複数のコードを並べて比較したりする時にも役立つよ。
multi monitorとは。
情報技術の用語で、『複数の画面』という意味の『マルチモニター』(別の言い方で『マルチディスプレー』とも言う)について
はじめに

机の上の景色が一変する、そんな魔法のような方法があります。それは画面を複数使うこと、つまりマルチモニターというものです。たった一つの画面と向き合っていた時とは全く違う、広々とした作業空間が目の前に現れます。このマルチモニターは、パソコンを使う上での作業効率を上げるための、とても手軽で効果的な方法です。
一つ画面だけで作業をしていると、資料を開きながら文章を作成する際に、何度も画面を切り替えなければならず、時間と手間がかかってしまいます。また、多くの資料を同時に見比べたい時にも、一つ一つ順番に開いて確認するのは大変です。しかし、マルチモニターなら、複数の作業を同時進行できます。例えば、片方の画面で資料を確認しながら、もう片方の画面で文章を作成できます。資料を見比べるのも容易になり、作業の流れが格段にスムーズになります。まるで頭の中の考えをそのまま画面に映し出したかのような感覚で、作業に没頭できます。
マルチモニターによって得られるのは、作業効率の向上だけではありません。目の疲れを軽減したり、集中力を高めたりといった効果も期待できます。画面の切り替え動作が減るため、目の負担が少なくなり、長時間のパソコン作業でも疲れにくくなります。また、必要な情報が常に目に見える状態にあるため、思考が途切れにくくなり、集中力を維持しやすくなります。マルチモニターを導入することで、作業が速くなるだけでなく、質も向上すると考えられます。
この快適な作業環境を実現するために必要なものや、導入する上での注意点、マルチモニターを最大限に活用するための様々な工夫など、これから詳しく説明していきます。画面を複数並べるだけで、あなたのパソコン作業は劇的に変化するでしょう。ぜひ、最後まで読んで、マルチモニターの世界を体験してみてください。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 作業効率の向上 |
|
| 目の疲れ軽減 | 画面の切り替え動作が減るため、目の負担が少なくなる |
| 集中力の向上 | 必要な情報が常に目に見えるため、思考が途切れにくくなる |
| 作業の質の向上 | 作業が速くなるだけでなく、質も向上する |
複数画面を使う利点

机の上を広々と使えるように、画面を複数使うことで仕事の場所を広くすることができます。これは、まるで大きな机で作業しているかのような快適さをもたらします。例えば、文章を書いている時を想像してみてください。一つの画面で文章を書き進めながら、もう一つの画面で調べたいことを表示したり、参考にしたい資料を開いておくことができます。画面を切り替える手間が省けるので、思考の流れを保ちながら、スムーズに作業を進めることができます。
また、複数の仕事を同時に行う際にも、複数画面は非常に役立ちます。例えば、表計算ソフトで作った資料を見ながら、別の画面で企画書を作成することができます。資料の内容を確認するためにいちいち画面を切り替える必要がないため、時間の節約になり、仕事の効率も上がります。まるで複数の机で同時に作業を進めているような感覚です。
広い画面領域は、全体を把握しやすくするという利点もあります。例えば、複雑な計画を立てている時、複数の画面に関連情報を表示することで、計画の全体像を容易に把握することができます。全体像を把握しやすくなることで、より良い計画を立てることができます。また、絵を描いたり、動画を編集する作業をする人にとっても、広い作業領域は大きなメリットとなります。細かな部分までしっかりと確認しながら作業を進めることができます。まるで大きなキャンバスで絵を描いているかのような、あるいは広い編集室で動画を編集しているかのような感覚を味わうことができるでしょう。
このように、複数画面を使うことで、仕事の効率を上げ、思考を整理し、創造性を高めることができます。まるで、自分の仕事の能力が一段階上がったかのような体験をすることができるでしょう。
| メリット | 具体的な例 | 効果 |
|---|---|---|
| 広い作業スペースの確保 | 一つの画面で文章を書き、もう一つの画面で資料を表示 | 思考の流れを維持、スムーズな作業 |
| マルチタスクの効率化 | 表計算ソフトと企画書を同時に表示 | 時間の節約、作業効率向上 |
| 全体把握の容易化 | 複数の画面に関連情報を表示 | 計画の全体像把握、より良い計画立案 |
| 広い画面領域の活用 | 絵を描く、動画編集 | 細部確認、作業効率向上 |
導入方法

複数の画面をパソコンで使うための準備は、思いの外、手間がかかりません。まず、パソコンをよく見て、画面に出力するための接続口がいくつあるか確認します。近頃発売された持ち運びできるパソコンであれば、たいてい「エイチディーエムアイ」や「ディスプレイポート」といった接続口がついています。
次に、画面とパソコンをつなぐための線が必要です。線の種類は、パソコンと画面の接続口の形に合わせて選びます。同じ形の接続口同士でないと、線をつなぐことができませんので、注意が必要です。線をつないだら、パソコンの設定画面で、画面の配置や文字の大きさなどを調整します。「ウィンドウズ」という基本操作をするための仕組みが入ったパソコンであれば、「設定」を開き、「システム」を選び、さらに「画面」を選ぶと、画面の設定をする場所が見つかります。
画面の配置は、自分が使いやすいように自由に調整できます。たとえば、よく使う方の画面を真ん中に置き、もう一つの画面を横に置くといった配置が一般的です。二つの画面を同じ大きさで、上下に並べることもできますし、三つ以上の画面を使う場合は、真ん中の画面を大きくし、周りの画面を小さくするといった配置も可能です。自分の使い方や好みに合わせて、画面の大きさや配置を調整することで、作業効率を上げたり、より快適にパソコンを使うことができます。
画面の配置だけでなく、文字の大きさも調整できます。小さな文字が見にくい場合は、文字を大きくしたり、画面全体を拡大表示することも可能です。また、画面の色合いや明るさも調整できるので、目の疲れを軽減するためにも、自分に合った設定を見つけ出すことが大切です。複数の画面を使うことで、資料を見ながら作業したり、動画を見ながら作業したりと、様々な作業が同時に行えるようになります。慣れるまでは少し時間がかかるかもしれませんが、一度使い始めると、その便利さに驚くことでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 接続口の確認 | パソコンに搭載されているHDMIやDisplayPortなどの出力ポートを確認する |
| 接続線の準備 | パソコンと画面の接続口に合ったケーブルを用意する |
| 画面設定 | Windowsの場合、「設定」>「システム」>「画面」で画面の配置、文字の大きさ、色合い、明るさなどを調整する |
| 画面配置 | よく使う画面を中央に配置したり、画面の大きさを変更したりと、自由にカスタマイズ可能(例:左右配置、上下配置、中央大画面+周辺小画面など) |
| 文字の大きさ | 文字サイズや画面の拡大率を調整することで、見やすさを向上させる |
| 画面の色合い・明るさ | 目の疲れを軽減するために、適切な色合いと明るさに調整する |
選び方のポイント

画面を見る機器を選ぶ際は、使う目的や置く場所の広さに合った大きさや画面の細かさのものを選びましょう。仕事の内容によっては、同じ大きさで同じ細かさの画面を複数台用意した方が良い場合もあります。加えて、画面の高さを変えたり、角度を調節できる台があれば、より快適な仕事場を作ることができます。画面の高さが合わなかったり、角度が不適切だと、肩こりや目の疲れの原因となるので、人の体の仕組みや特徴に合わせた調節が大切です。
画面の色の見え方や明るさも仕事の効率に影響を与えます。例えば、書類を作る際は文字が読みやすい自然な白さが求められますが、写真や動画を編集する際は色の正確さや鮮やかさが重要になります。また、画面の明るさは周囲の明るさに合わせて調整する必要があります。明るすぎると目が疲れやすく、暗すぎると見づらくなってしまいます。そのため、自分の好みに合わせて、作業内容に適した色や明るさに調節しましょう。
画面を見る機器を選ぶ際には、接続方法も確認しましょう。パソコンにつなぐ場合は、HDMI端子やDisplayPort端子など、パソコンに対応した接続方法を選びます。また、ゲームで使う場合は、応答速度の速い画面を選ぶと、残像感が少なく滑らかな映像でゲームを楽しむことができます。応答速度が遅いと、動きの速い場面で残像感が生じ、ゲームの操作に影響が出ることがあります。このように、画面を見る機器を選ぶ際は、使う目的や環境に合わせて、様々な要素を考慮することが大切です。快適な作業環境やエンターテイメント環境を実現するために、画面の大きさ、細かさ、高さ、角度、色の見え方、明るさ、接続方法などをよく確認し、自分に合った機器を選びましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 画面の大きさ | 使う目的や置く場所の広さに合わせる |
| 画面の細かさ | 使う目的や置く場所の広さに合わせる。場合によっては複数台用意する。 |
| 高さ・角度 | 調節可能な台を使用し、肩こりや目の疲れを防ぐ。 |
| 画面の色 | 作業内容に合わせる(例:書類作成には自然な白、写真・動画編集には正確で鮮やかな色) |
| 画面の明るさ | 周囲の明るさに合わせて調整し、目の疲れや見づらさを防ぐ。 |
| 接続方法 | パソコンの端子に合ったものを選ぶ(例:HDMI, DisplayPort)。ゲーム用途では応答速度の速いものを選ぶ。 |
注意点
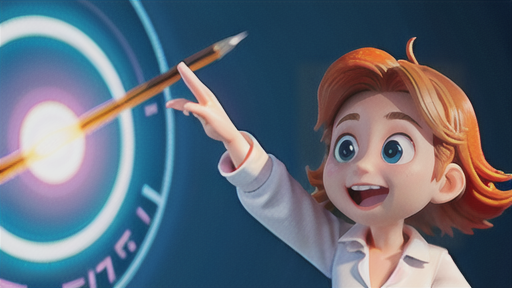
{複数の画面を使う環境を作る時は、機械の力にも気を配る必要があります。}特に、きめ細かい画面をたくさん使う場合は、画面の描画をつかさどる部品の性能が足りないと、画面の動きが遅れたり、滑らかでなくなったりすることがあります。そのため、気持ちよく作業するには、ある程度の性能を持つ機械が必要です。
たとえば、4K画面を3つ繋ごうとする場合、単純計算でフルハイビジョン(1920×1080)画面の4倍のきめ細かさを持つ画面を3つ同時に処理する必要があるため、とても高い性能が要求されます。フルハイビジョン画面1枚の表示に比べ、12倍の処理能力が要求されることになります。このため、画面の描画をつかさどる部品には、最新の、高性能のものを選ぶ必要があります。画面の描画性能が低い部品を選んでしまうと、動画編集や3Dの設計など、高い性能を要求される作業を行う際に、作業が滞ってしまい、作業効率が落ちてしまう可能性があります。
また、画面をたくさん使うと、使う電気の量も増えます。そのため、電気供給の力にも気を配る必要があります。特に、据え置き型の機械の場合は、電気供給部品の容量が足りているかを確認しましょう。電気供給部品の容量が不足していると、機械が不安定になったり、最悪の場合は故障する可能性があります。
最後に、配線が絡まらないように、配線をまとめる道具などを使って整理整頓しましょう。配線が整理されていないと、見た目も悪いだけでなく、配線の抜き差しもしにくくなり、トラブルの原因にもなります。また、ホコリが溜まりやすく、火災の危険性も高まります。整理整頓することで、快適な作業環境を維持することができます。
| 項目 | 注意点 | 理由 |
|---|---|---|
| 画面描画性能 | 高性能な部品を選ぶ | 画面の動きが遅れたり、滑らかでなくなったりするのを防ぐため。動画編集や3D設計など、高い性能を要求される作業を行う際に、作業が滞ってしまうのを防ぐため。 |
| 電気供給 | 電気供給部品の容量を確認する | 機械が不安定になったり、故障するのを防ぐため。 |
| 配線 | 配線をまとめる道具などを使って整理整頓する | 見た目も悪く、配線の抜き差しもしにくくなり、トラブルの原因になるのを防ぐため。ホコリが溜まりやすく、火災の危険性も高まるのを防ぐため。 |
まとめ

複数の画面を使う「複数画面表示」は、机の上を広々と使えるだけでなく、仕事の効率も大きく上げてくれる便利な方法です。パソコンを使った仕事で成果を上げたいと考えている方には、ぜひおすすめしたいです。 この記事では、複数画面表示を取り入れるメリットやその方法について説明しました。
複数画面表示の一番の利点は、複数の作業を同時に行えることです。例えば、資料を見ながら文章を作成する場合、画面をいちいち切り替える必要がなく、両方を同時に見比べながら作業できます。また、大きな表計算ソフトを複数の画面に広げて表示したり、設計図面などの大きな画像を細部まで確認しながら作業することも可能です。このように、複数画面表示は作業の手間を省き、時間を有効に使えるようにしてくれます。
複数画面表示の設定方法は意外と簡単です。必要なものは、画面を接続するためのケーブルと、パソコンに対応した出力端子があるかどうかを確認することだけです。ほとんどのパソコンには複数の出力端子が備わっているので、簡単に設定できるでしょう。費用についても、画面自体は比較的手頃な価格で購入できるので、大きな投資をすることなく導入できます。
複数画面表示を初めて使う方は、最初は少し使いにくいと感じるかもしれません。しかし、一度慣れてしまえば、その便利さからもう元の画面構成には戻れなくなるでしょう。快適な作業環境は、集中力を持続させ、意欲を高め、良い結果に繋がります。この記事で紹介した内容を参考に、自分に合った複数画面表示環境を作って、快適なパソコン作業を体験してみてください。
| メリット | 方法 | 費用 | その他 |
|---|---|---|---|
| 複数の作業を同時に行える 例:資料を見ながら文章作成、大きな表計算ソフトの表示、設計図面などの確認 作業の手間を省き、時間を有効に使える |
画面を接続するためのケーブルと、パソコンに対応した出力端子が必要 ほとんどのパソコンには複数の出力端子が備わっている |
画面自体は比較的手頃な価格 | 最初は使いにくいと感じるかもしれないが、慣れれば便利 快適な作業環境は、集中力を持続させ、意欲を高め、良い結果に繋がる |
