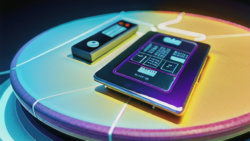ハードウエア
ハードウエア ハードディスクの仕切り「パーティション」とは?
パソコンの中にデータを保存しておくための部品であるハードディスクは、広大な記憶領域を持っています。この広大な領域を、用途に応じていくつかの領域に分けて使うことを「ハードディスクの分割」と言います。
ハードディスク全体を一つの大きな部屋だと考えてみましょう。この部屋を、仕事道具を置く場所、洋服をしまう場所、寝るための場所、といったように、いくつかの部屋に分けて使うと便利です。ハードディスクの分割は、この部屋に仕切りを設けて、用途に合わせて複数の領域に区切ることと同じです。それぞれの領域は「パーティション」と呼ばれ、仕事用、個人用データ保存用、システム用など、異なる目的のために使用されます。
ハードディスクを分割する最大のメリットは、データの整理整頓がしやすくなることです。例えば、システムファイルと個人用データを同じ場所に保存していると、システムトラブル発生時に、個人用データも巻き込まれてしまう可能性があります。しかし、ハードディスクを分割して、システムファイルと個人用データを別々のパーティションに保存しておけば、万が一システムに問題が発生した場合でも、個人用データは守られる可能性が高くなります。
また、複数のオペレーティングシステム(OS)をインストールしたい場合にも、ハードディスクの分割は必須です。OSはそれぞれ独立した領域を必要とするため、パーティションを作成して、それぞれのOSに専用の領域を割り当てる必要があります。
このように、ハードディスクの分割は、パソコンをより便利に、そして安全に使うために有効な手段です。