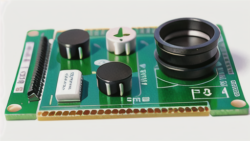デバイス
デバイス ウルトラモバイルPC:ポケットサイズの未来
- ウルトラモバイルPCとは2006年、マイクロソフト社とインテル社が共同で発表したのが、ウルトラモバイルPCと呼ばれる、持ち運びやすさを重視した超小型パソコンの規格です。従来のノートパソコンと比較して格段に小さく、携帯電話よりも大きな画面を搭載している点が特徴で、モバイル機器とノートパソコンの中間的な存在として注目を集めました。ウルトラモバイルPCは、外出先でも手軽に使えることを目的として開発されました。小型軽量であるため、カバンに入れての持ち運びが容易で、外出先での作業や情報収集に最適です。また、バッテリー駆動時間が長いことも特徴の一つで、電源の確保が難しい場所でも長時間使用することができます。当初は、小型化による処理能力の低さや、画面の小ささなどが課題として挙げられていましたが、技術の進歩とともに、これらの課題は克服されつつあります。現在では、高性能なCPUや大容量のメモリを搭載したモデルも登場しており、ノートパソコンに匹敵する性能を備えています。ウルトラモバイルPCは、その携帯性と機能性の高さから、ビジネスパーソンや学生を中心に、幅広い層に利用されています。今後も、技術革新によって更なる進化が期待される分野と言えるでしょう。