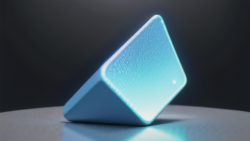ハードウエア
ハードウエア マウント:機器接続の仕組み
計算機に周辺機器を繋ぐ際には、計算機がその機器を認識し、使えるようにする手順が必要です。この準備の手順を「組み込み」と呼びます。これは、外付けの記憶装置やUSB記憶装置などを計算機に繋げた際に、自動的に行われる処理です。この処理のおかげで、繋げた機器に保存されている情報を読んだり、新たな情報を書き込んだりすることが可能になります。「組み込み」という言葉は、山の頂上(組み込み)に登って景色を一望するように、計算機からも繋げた機器の中身全体が見えるようになる様子を表現しています。
この「組み込み」の処理は、周辺機器を使う上で非常に大切です。もしこの処理が正しく行われなければ、計算機は繋げた機器を認識することができず、情報を読み書きすることもできません。例えば、外付けの記憶装置を繋いだのに、計算機上でその装置が表示されない場合は、「組み込み」がうまくいっていない可能性があります。このような時は、接続を確認したり、計算機を再起動したりすることで解決する場合があります。また、機器自体に問題がある場合もありますので、別の計算機に繋いでみるなど、様々な確認が必要です。
「組み込み」された機器は、計算機の一部として扱われます。例えば、外付けの記憶装置を「組み込み」すると、計算機の記憶領域が増えたように扱うことができます。USB記憶装置も同様に、「組み込み」することで、その中に保存されている写真や文章などを、計算機で直接開いたり編集したりすることができるようになります。この「組み込み」という処理は、様々な周辺機器を計算機で活用するための、なくてはならない重要な役割を果たしていると言えるでしょう。まるで、計算機という建物に新しい部屋を増築するようなイメージです。増築した部屋を自由に使えるように、「組み込み」という作業が必要なのです。