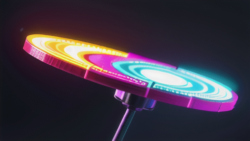ハードウエア
ハードウエア 磁気ディスク:情報の宝庫
磁気ディスクとは、情報を磁気の力で保存する記憶装置です。薄い円盤状の部品に、磁石の性質を持つ物質(磁性体)が塗られています。この磁性体の向きを細かく変えることで、0と1のデジタル情報を記録します。情報を書き込む際は、磁気ヘッドと呼ばれる小さな部品が、回転する円盤上を動きます。この磁気ヘッドが磁界を発生させ、円盤上の磁性体の向きを北向きまたは南向きに変えます。この向きの違いが、0か1かのデータを表すのです。
データを読み出す際も、磁気ヘッドが活躍します。磁気ヘッドは、円盤上の磁性体の向きを感知し、それを電気信号に変えます。北向きの磁性体からは正の電気信号、南向きの磁性体からは負の電気信号が発生します。こうして、0と1のデジタル情報が復元され、コンピュータで利用できるようになります。
身近な例としては、コンピュータの中に組み込まれているハードディスクが挙げられます。ハードディスクは、複数の磁気ディスクを積み重ねた構造で、大容量の情報を保存できます。また、かつてはフロッピーディスクも広く使われていました。フロッピーディスクは、柔らかいプラスチックケースに磁気ディスクを一枚入れたもので、持ち運びに便利でした。
磁気ディスクは、電気を流さなくても情報を保持できるという大きな利点があります。そのため、コンピュータの電源を切っても、保存した情報は消えません。この特徴から、長年にわたり、情報の保存手段として広く利用されてきました。近年は、より高速で小型な記憶装置が登場していますが、磁気ディスクは今でも大容量の情報を保存する際に重要な役割を担っています。