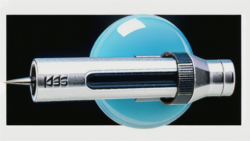開発
開発 固定小数点形式:整数だけで小数を扱う
- 固定小数点形式とは固定小数点形式は、数値の表現方法の一つで、小数点を常に一定の位置に固定して扱う方式です。コンピュータ内部では、全ての情報は「0」と「1」の組み合わせで表現されます。この表現方法は整数と相性が良いのですが、小数を扱う場合は工夫が必要になります。そこで用いられるのが、固定小数点形式です。この方式では、あたかも小数点が存在するかのように整数を用いて数値を表現し、計算を行います。例えば、小数点以下2桁を固定する場合を考えてみましょう。この場合、1.23という数値は、実際には小数点を持たない123という整数として扱われます。同様に、0.05は5として扱われます。固定小数点形式の利点は、計算資源が限られた環境でも効率的に小数を扱うことができる点です。整数演算と同じ仕組みで計算できるため、処理が高速になります。また、表現方法が単純であるため、プログラムも簡潔になります。一方で、固定小数点形式は表現できる数値の範囲が限られるという欠点もあります。小数点の位置を固定しているため、小さな数値や大きな数値を正確に表現できない場合があります。