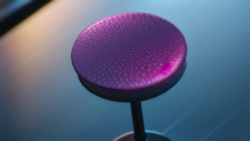ハードウエア
ハードウエア 電源を切っても大丈夫? 身近な記憶装置 フラッシュメモリの仕組み
近年、スマートフォンやデジタルカメラ、ゲーム機など、私たちの生活は様々な電子機器であふれています。これらの機器には、写真や動画、音楽、ゲームのデータなど、多くの情報を記憶しておくための装置が欠かせません。こうした電子機器に搭載される記憶装置の中で、特に幅広く活用されているのが「フラッシュメモリ」です。
フラッシュメモリは、電源を切っても記憶した情報を保持できるという特徴があります。そのため、持ち運びに便利なスマートフォンやデジタルカメラ、ゲーム機などに最適です。例えば、スマートフォンで撮影した写真を、電源を切っても後で見返すことができるのは、フラッシュメモリのおかげです。
また、フラッシュメモリは、読み書きの速度が速いという点も大きなメリットです。そのため、起動やデータの読み込みに時間がかかると不便なスマートフォンやゲーム機などにも適しています。
さらに、フラッシュメモリは、衝撃や振動に強いという特徴も備えています。この特徴から、持ち運んで使用することが多い機器でも、安心して使うことができます。
このように、フラッシュメモリは、小型で軽量、そして衝撃に強いという特性から、様々な電子機器に搭載され、私たちの生活をより便利で豊かなものにしています。