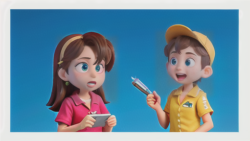インフラ
インフラ 止まらない仕組み:ホットスタンバイ
近ごろの世の中は、情報技術なしでは成り立ちません。会社での仕事や普段の暮らしの中で、計算機組織が滞りなく動くことは欠かせません。もし組織が止まれば、仕事が遅れたり、お客さまへのサービスが滞ったり、お金の損失が出たりと、いろいろな問題が起きるかもしれません。だからこそ、組織の信頼性を高め、何かトラブルが起きた時でもすぐに復旧できる仕組みが必要なのです。
ホットスタンバイとは、このような課題を解決する有効な手段の一つです。これは、メインで稼働している計算機組織とは別に、予備の組織を常に待機させておく仕組みです。もしメインの組織に何かトラブルが起きても、待機している予備の組織がすぐに仕事を引き継ぎます。そのため、サービスを止めることなく、お客さまに影響を与えずに済むのです。
ホットスタンバイ方式では、予備の組織にもメインの組織と同じ情報が常に送られています。つまり、メインの組織が停止した瞬間から、予備の組織は最新の状態で稼働を開始できるのです。このおかげで、切り替えにかかる時間が非常に短く、復旧までの時間を大幅に短縮できるという利点があります。
ホットスタンバイは、銀行のオンラインシステムや、通信会社のネットワーク設備、インターネット上のサービスなど、高い信頼性が求められる様々な場面で活用されています。システム停止が許されない状況において、ホットスタンバイはなくてはならない技術と言えるでしょう。ホットスタンバイを導入することで、安定したサービス提供を実現し、顧客満足度を高め、ひいては企業の信頼性向上にも繋がるのです。