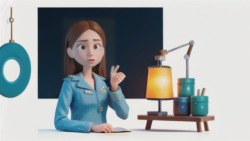セキュリティ
セキュリティ 知っておくべき、あの番号:製品認証の鍵
家電量販店やインターネットを通じて、パソコンの使える道具や遊び道具を手に入れたとき、ほとんどの場合に「製品番号」と呼ばれるものが付いてきます。この番号は、最近では「製品の鍵」や「製品の証明番号」、「一続きの番号」などとも呼ばれ、自分が買ったものが正式なものであることを示す大切な役割を担っています。一見すると、ただ数字が並んでいるだけのように見えますが、この短い番号には、作った人の権利を守り、不正な使い方を防ぐといった大きな意味が込められています。この番号があるおかげで、私たちは安心して道具や遊び道具を使うことができるのです。
この製品番号は、いわば製品の「身分証明書」のようなものです。製品一つ一つに割り当てられた固有の番号であり、これによって正規品であることが確認できます。もしもこの番号がなければ、不正にコピーされたものが出回ってしまい、作った人の努力が無駄になってしまうかもしれません。また、私たちも偽物をつかまされるリスクが高まります。製品番号は、作った人と使う人、双方を守る大切な仕組みなのです。
製品番号にはいくつかの種類があります。例えば、パッケージ版の道具に印刷されているもの、インターネットでダウンロードした場合に表示されるもの、あるいはメールで送られてくるものなどです。表示形式も様々で、数字だけのもの、アルファベットと数字が混ざったものなどがあります。いずれの場合も、大切に保管しておく必要があります。
製品番号は、再インストールやサポートを受ける際などに必要になります。紛失してしまうと、せっかく買った道具が使えなくなってしまう可能性もあります。そのため、購入後は大切に保管し、必要に応じてすぐに確認できるようにしておくことが重要です。メモ帳に書き写したり、写真を撮ったり、あるいは専用の管理道具を使うなど、自分に合った方法で保管しましょう。
この大切な番号について、その役割や種類、注意点などをこれから詳しく見ていきましょう。