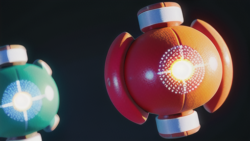ハードウエア
ハードウエア ブルースクリーンの謎を解く
電算機を使っていると、画面全体が青色になり白い文字で何やら表示されることがあります。この表示は、よく「青画面」と呼ばれ、電算機を使う人にとってあまり見たくない画面の一つです。正式には「死の青画面」と呼ばれ、英語では「ブルー スクリーン オブ デス」と表現され、略して「死の青画面」と呼ばれることもあります。「死」という言葉が使われているのは、この画面が表示された時、電算機の中枢部分である系統が深刻な不具合状態にあることを示すからです。つまり、電算機が正常に動かなくなる、例えるなら「死んだ」状態にあることを意味します。
この青画面は、電算機の心臓部ともいえる基本処理系統に重大な問題が発生した時に表示されます。基本処理系統は電算機全体の動きを制御する重要な役割を担っています。そのため、基本処理系統が停止してしまうと、電算機も正常に動かなくなってしまいます。青画面は、電算機にとって非常に深刻な事態であることを示す警告なのです。
青画面には、エラーの状況を示す情報が表示されます。専門家はこの情報を見て、不具合の原因を特定します。技術の進歩により、最近の青画面は以前のものより幾分わかりやすい表現でエラー内容を示すようになっています。しかし、多くの利用者にとって、青画面に表示される専門用語や暗号のような文字列は難解です。
青画面が表示された場合、まずは画面に表示されている情報を記録しましょう。専門家に相談する際に役立ちます。多くの場合、電算機を再起動することで復旧できますが、再起動を繰り返しても青画面が表示される場合は、基本処理系統や記憶装置、その他部品に問題がある可能性があります。このような場合は、専門家の助言や修理が必要となるでしょう。