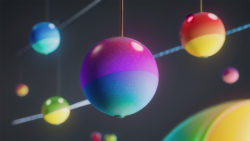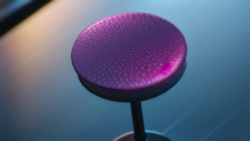デザイン
デザイン 製造業の進化!CAD/CAMとは?
近年、製造業において「CAD/CAM」という言葉を耳にする機会が増えてきました。製品の設計から製造までの工程をコンピューターで一貫管理するシステムを指し、従来の手作業で行っていた設計や製造の工程をデジタル化することで、業務効率化や品質向上を実現する強力なツールとして注目されています。
「CAD」は「Computer Aided Design(コンピュータ支援設計)」の略称で、コンピューターを用いて製品の設計図を作成します。従来は手書きで行っていた設計図面をデジタル化することで、設計の修正や修正履歴の管理、3次元データの作成などが容易になります。また、設計データをもとにシミュレーションを行うことで、製品の性能や強度を事前に確認することも可能となり、開発期間の短縮やコスト削減にも繋がります。
一方、「CAM」は「Computer Aided Manufacturing(コンピュータ支援製造)」の略称であり、設計データをもとにコンピューターで工作機械を制御し、製品を自動で製造します。これにより、手作業による製造時に発生する個人差をなくし、高精度で均質な製品を効率的に生産することが可能となります。
CAD/CAMは、従来の製造プロセスに革新をもたらし、製造業全体の進化を加速させています。設計から製造までのプロセスをシームレスに繋ぐことで、業務効率化、品質向上、コスト削減を実現し、企業の競争力強化に大きく貢献します。