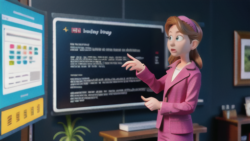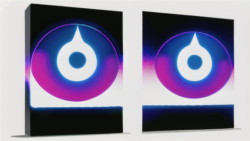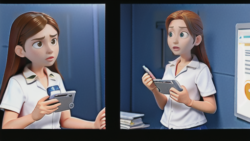ハードウエア
ハードウエア PowerPC: アップルを支えた強力な頭脳
1991年、コンピューター業界に激震が走りました。当時、業界を牽引していたアップル、IBM、モトローラという三社の巨人が、手を組んだというニュースは、多くの人々に驚きをもって迎えられました。三社が共同で開発に乗り出したのは、「PowerPC」と名付けられた新しいマイクロプロセッサーです。 当時のマイクロプロセッサーは、複雑な命令セットを持つCISC型が主流でしたが、PowerPCはより高速な処理を可能にするRISC型を採用しました。RISC型は命令セットを簡略化することで、処理の高速化を図る設計思想です。このPowerPCの登場は、パーソナルコンピューターの高性能化を一気に加速させる存在として、大きな期待を集めました。 従来は、それぞれ独自の戦略で開発を進めていた三社が、PowerPCの開発で協調路線を歩み始めた背景には、マイクロソフトとインテルによる「Wintel」連合の市場席巻がありました。PowerPCは、このWintel連合に対抗し、コンピューター業界の勢力図を塗り替える切り札として期待されていたのです。