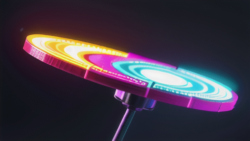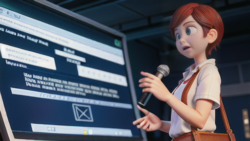開発
開発 DHTML:動的なウェブページを実現する技術
- DHTMLとはDHTMLは"Dynamic HTML"の略称で、その名の通り動的なウェブサイトを構築するための技術です。従来のHTMLでは、一度ウェブページを読み込むと、そこに表示される情報は静的なものでした。しかしDHTMLを用いることで、ユーザーの操作や時間の経過に合わせて、表示内容を変化させることが可能になります。DHTMLは、HTML、CSS、JavaScriptという三つのウェブ標準技術を組み合わせることで実現されます。 HTMLはウェブページの構造を、CSSは見た目やスタイルを、そしてJavaScriptは動作や機能をそれぞれ司っています。 DHTMLはこれらの技術を連携させることで、静的なHTML文書に動的な要素を追加し、よりリッチなユーザー体験を提供します。例えば、マウスの動きに合わせて画像が変化したり、ボタンをクリックすると隠れていたメニューが表示されたりするような、インタラクティブな要素をウェブサイトに組み込むことができます。 DHTMLは、従来のHTMLでは実現が難しかった、表現力豊かなウェブサイトを構築するための技術と言えるでしょう。