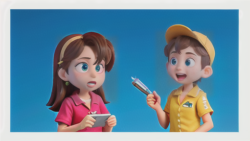ネットワーク
ネットワーク FTTR:高速インターネットをもっと身近に
- 光ファイバーをもっと身近に!FTTRとは?近年、動画配信サービスの普及やリモートワークの増加に伴い、高速で安定したインターネット回線への需要が高まっています。その中で注目を集めているのが「FTTR」という新しいインターネット接続サービスです。FTTRは、「Fiber To The Remote Terminal」の略称で、光ファイバーをより利用者の近くに引き込むことで、高速かつ安定したインターネット環境を実現します。従来の光回線サービスであるFTTP(Fiber To The Premises)では、光ファイバーを建物の共有部分まで引き込み、そこから各部屋へは既存の電話線やLANケーブルなどを利用して接続していました。一方、FTTRでは、光ファイバーを各部屋に設置する装置(リモートターミナル)まで直接引き込みます。そのため、従来のFTTPと比較して、より高速で安定した通信が可能となります。FTTRの導入には、いくつかのメリットがあります。まず、工事期間が短いことが挙げられます。FTTPのように、建物内の配線を変更する必要がないため、短時間で工事を完了することができます。また、工事費用も比較的安価である点も魅力です。さらに、FTTRは、将来的に高速化の需要が高まった場合でも、設備の変更なしに対応できるというメリットもあります。このように、FTTRは、高速性、安定性、導入のしやすさなど、多くのメリットを持つインターネット接続サービスです。今後、FTTRは、ますます普及していくことが予想されます。