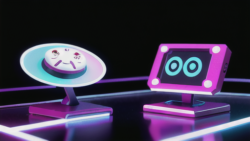ハードウエア
ハードウエア 286:進化した頭脳
一九八二年、計算機の心臓部と言えるマイクロプロセッサ、二八六が登場しました。正式名称は八〇二八六といい、インテル社が開発を手がけました。これは、それまでの八〇八六という部品と比べて、処理の速さや記憶領域の管理能力が格段に上がった画期的なものでした。
この二八六の登場は、計算機がより複雑な仕事を行えるようになることを意味していました。以前は難しかった高度な計算も、二八六によって可能になったのです。これは当時の技術の進歩を大きく後押しし、様々な分野に影響を与えました。
二八六は、従来の十六ビット構造という仕組みを受け継ぎつつ、保護方式という新しい機能を備えていました。これは、記憶領域の使い方をより効率的にする画期的な仕組みでした。このおかげで、大きな容量のプログラムを実行できるようになり、複数の仕事を同時に行う、いわゆる並行処理への道も開かれました。
二八六の登場は、個人向け計算機の進化における大きな一歩となりました。その後の技術発展に多大な影響を与え、計算機の歴史に大きな足跡を残したのです。処理能力の向上と記憶領域管理機能の強化により、より高度な応用ソフトの開発が可能になりました。その結果、計算機は仕事や研究など、様々な場所で活用されるようになったのです。まさに、計算機がより身近で強力な道具へと進化する過程における重要な転換点と言えるでしょう。