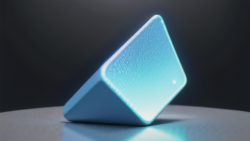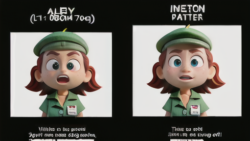その他
その他 新規保存:初めての保存
新しく作った書類や絵、音声などの資料を、コンピューターの中の記憶する場所に書き込むことを新規保存といいます。初めて作ったファイルなら、どんな種類でも新規保存が必要です。この作業をすることで、作った資料が、コンピューター本体の記憶装置や、外付けの記憶装置に記録されます。そうすれば、後でまたその資料を開いて見たり、使ったりすることができるようになります。
ファイルを作っただけでは、コンピューターの一時的な記憶場所に置かれているだけです。これは、机の上で作業しているような状態です。机の上では作業できますが、片付けるときにしまわないと無くなってしまいます。同じように、コンピューターの電源を切ったり、作業していたソフトを閉じると、一時的な記憶場所にあるものは消えてしまいます。作った資料を無くさないためには、必ずきちんと保存する場所を決めて、そこにしまっておく必要があります。これが新規保存です。
新規保存をするときには、まず保存するファイルに名前をつけます。これは、本棚にしまう本にタイトルをつけるようなものです。名前をつけると、後で探しやすくなります。次に、どこに保存するかを決めます。コンピューターの中のどの場所に置くか、あるいは外付けの記憶装置に置くかなど、好きな場所を選べます。本棚のどの段に置くか、別の部屋の本棚に置くかを決めるようなものです。保存する場所を決めたら、そこで初めてファイルがしっかりと記憶装置に書き込まれ、電源を切っても、ソフトを閉じても消えなくなります。