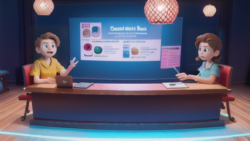デバイス
デバイス 懐かしい記憶媒体 フロッピーディスク
フロッピーディスクは、1980年代から1990年代前半にかけて、パソコンやワープロ専用機などでデータの保存に使われていた記録媒体です。
薄い円形の磁気ディスクを、柔軟性のあるプラスチック製のジャケットで覆っているのが特徴です。この柔軟性から「フロッピー」という名前が付けられました。
フロッピーディスクは、当時のコンピュータの記録媒体としては小型で持ち運びが容易だったため、データのやり取りや持ち運びに広く利用されました。
容量は時代と共に増加しましたが、それでも現代の記録媒体と比べるとはるかに小さく、一枚のフロッピーディスクに保存できるデータ量は限られていました。
2000年代以降、CD-RやUSBメモリなど、より大容量で高速な記録媒体が登場したことにより、フロッピーディスクは次第に使われなくなりました。
現在では、フロッピーディスクはほとんど使われていませんが、一時代を築いた記録媒体として、コンピュータの歴史において重要な役割を果たしました。