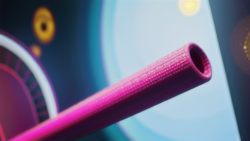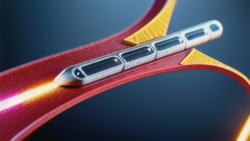デバイス
デバイス 全画面表示のススメ
- 全画面表示とはパソコンやスマートフォンなど、私たちが日々利用するデジタル機器には画面があり、そこには様々な情報が表示されます。この画面に表示される情報の一つに「ウィンドウ」があります。ウィンドウは、インターネットのページや資料、写真など、個々の情報を表示するための枠組みです。普段私たちが目にするウィンドウには、情報を整理するための様々な要素が表示されています。例えば、ウィンドウの一番上には「タイトルバー」があり、開いているページや資料の名前が表示されます。また、画面の上部や下部には「メニューバー」や「スクロールバー」があり、ウィンドウ内の操作や表示範囲の調整を行うことができます。「全画面表示」とは、これらのウィンドウ周りの要素を一時的に非表示にし、ウィンドウの中身だけを画面いっぱいに拡大して表示する方法です。動画配信サービスで映画を視聴する際や、ゲームに集中したい際に利用すると、より臨場感あふれる体験ができます。全画面表示を行うには、キーボードの特定のキーを押したり、マウス操作で専用のボタンをクリックしたりします。解除する際も同様の方法で行うことができ、ウィンドウは元の大きさに戻り、タイトルバーなどの要素も再び表示されます。