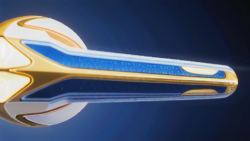開発
開発 多バイト文字を理解する
- 文字を数字に変換する仕組み
私たちが普段何気なく使っている文字は、コンピュータ内部では数字として処理されています。画面に表示される「あ」という文字も、プログラムで扱う「A」という文字も、コンピュータにとってはすべて数字の羅列でしかないのです。
では、どのようにして文字と数字が対応付けられているのでしょうか?
その答えが「文字コード」です。文字コードとは、文字と数字の対応表のようなもので、それぞれの文字に特定の数字を割り当てています。例えば、広く使われている文字コードの一つであるASCIIコードでは、「A」という文字は「65」という数字に対応しています。「B」は「66」、「C」は「67」と続き、数字が増えるごとにアルファベット順に文字が割り当てられています。
コンピュータはこの文字コードを使って、文字を表示したり、処理したりしています。私たちが入力した文字は、キーボードを通してまず文字コードに変換され、コンピュータ内部で処理された後、再び文字コードに基づいて画面に表示されます。文字コードは、人間とコンピュータが文字情報をやり取りするために欠かせない、重要な役割を担っているのです。